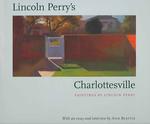出版社内容情報
明快で痛快な「クラシック音楽の本質と粋」
著者は、サントリー学芸賞・吉田秀和賞ほか受賞多数、NHK・Eテレ「スコラ」(坂本龍一の音楽番組)出演でも知られる京大教授・岡田暁生氏。岡田氏が、ベストセラー『西洋音楽史』と『音楽の聴き方』の粋をよりわかりやすく、より楽しめる1冊として入門者向けに仕立てました。かつ新しい視点も交えて従来の岡田ファンも充分満足する内容になっています。
「音楽史の流れ」「モーツァルトとベートーヴェンの違いについて」などの、ありがちな項目から「うんざりするほど長い音楽について」「ワケのわからない音楽について」など、この手の本にはなかった項目まで、40のキーワードを駆使して「クラシック音楽の本質と粋」が解説されています。全編320ページのボリュームで書かれたクラシック音楽の本が、一度読み始めるととまらない極上のエンタテインメントとなっています。
岡田 暁生[オカダ アケオ]
著・文・その他
内容説明
入門者も、通も思わず叫んだ「えっ、そうだったの!」目からウロコのクラシック音楽の死角。
目次
「クラシック音楽」の黄金時代は一九世紀
音楽史の流れ―ウィーン古典派まで
ロマン派は自己表現する
「現代音楽」と二〇世紀
交響曲はクラシックのメインディッシュ
交響曲は一九世紀の頑張りソング?
交響曲にはなぜ複数の楽章があるのか?
オペラは「クラシック」じゃない?
サロンの物憂いプレイボーイたちの音楽
家庭音楽とドイツ教養市民〔ほか〕
著者等紹介
岡田暁生[オカダアケオ]
音楽学者。京都大学人文科学研究所教授、文学博士。1960年京都生まれ。著書に『オペラの運命』(中公新書・2001年サントリー学芸賞受賞)、『西洋音楽史「クラシック」の黄昏』(中公新書・2005年)、『ピアニストになりたい!19世紀もうひとつの音楽史』(春秋社・2009年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞)、『音楽の聴き方 聴く型と趣味を語る言葉』(中公新書・2009年吉田秀和賞受賞)ほか多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あやの
1959のコールマン
おせきはん
trazom
ムーミン2号
-
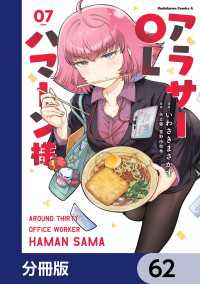
- 電子書籍
- アラサーOLハマーン様【分冊版】 62…
-
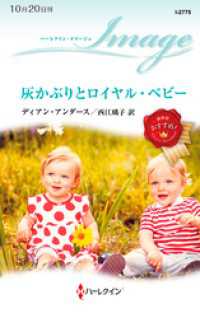
- 電子書籍
- 灰かぶりとロイヤル・ベビー ハーレクイン