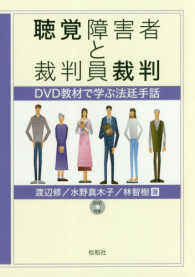出版社内容情報
新宿が最も輝いていた頃の愛と情熱の物語
本格的インドカリーで全国的にも有名な新宿中村屋。2014年10月、リニューアルした同社新ビル内に美術館がオープンした。
明治時代末期から大正、昭和初期にかけて、同社の創業者である相馬愛蔵・黒光夫妻のもとには多くの芸術家が集い、サロンとして文化を発信。ロダンに影響を受け日本の彫刻界に大きな足跡を残した荻原碌山や詩人の高村光太郎、書家の會津八一らが出入りし活況を呈していた。そしてインドの独立運動家をかくまい、ロシアの詩人を援助し、それらがきっかけでインドカリーやボルシチなど名物料理が生まれていく。
この「中村屋サロン」を中心に花開いた芸術と食文化を、愛と情熱に溢れた人間模様とともに描いた、知られざる新宿ヒストリー。
【編集担当からのおすすめ情報】
中村屋創業者の妻、相馬黒光は才気溢れる女性で芸術に理解を示しましたが、その考えや行動は当時としては破天荒で、「花子とアン」で話題になった白蓮にも似た魅力あるキャラクター。早逝した彫刻家・荻原碌山との許されざる恋は、かつてテレビドラマ化されています。
内容説明
明治末期から大正、昭和初期にかけて、活況を呈した中村屋サロン。彫刻家・荻原守衛(碌山)、高村光太郎、画家・中村彝…。激動の時代、彼らを支え、世のために尽くした相馬愛蔵・黒光夫妻の物語。
目次
第1章 士族の花嫁(世界の果て;兄と姉と弟;仙台の家 ほか)
第2章 書生パン屋(ふたたび峠を越える;居抜きの店;商売の「快味」 ほか)
第3章 彫刻家の誕生(極貧留学生;ロダンとの出会い;自然を師とする ほか)
第4章 サロンの人々(碌山の置き土産;インドの志士;エロシェンコ ほか)
終章 古き良き時代(中村屋の秘密;勝利の味のカリー;愛蔵と黒光の作ったもの ほか)
著者等紹介
石川拓治[イシカワタクジ]
1961年、茨城県水戸市生まれ。早稲田大学法学部卒。フリーランスライター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スプリント
あまね
憂霞
石橋