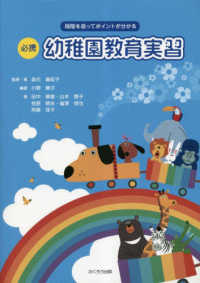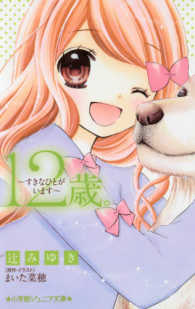出版社内容情報
「風俗画」の見方と魅力をわかりやすく解説
ルーヴル美術館が誇る、フェルメール《天文学者》をはじめ、レンブラントや ルーベンス、ティツィアーノ、ブーシェ、ヴァトー、ミレーなど、ヨーロッパ絵画の巨匠たちによる「風俗画」の名画の数々を、美麗な図版で紹介。また、「風俗画」の読み解き方や魅力を、展示場では見えないような部分の詳細な拡大図も用いてわかりやすく解説。さらに日本が誇る「風俗画」である「浮世絵」との比較で、理解と親近感を深めます。他に類を見ない、ビジュアル主体の「風俗画」入門書です。
本書は、2015年2月21日?9月27日という7ヶ月間余りの長期にわたり、東京・六本木の新国立美術館と京都市美術館の2会場で開催される(主催:日本テレビ)「ルーヴル美術館展 日常を描く――風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄」のオフィシャル・ブック。ルーヴル美術館館長や展覧会監修者らへのインタビューも含め、2015年話題の美術展の鑑賞ガイドとしても最適です。
尾崎 彰宏[オザキ アキヒロ]
監修
目次
第1章 「風俗画」の謎と魅力(なぜ「天文学者」はキモノを着ているのか?―フェルメール『天文学者』;「あの世の幸せ」と「この世の幸せ」を天秤にかける―マセイス『両替商とその妻』;ほんとうに騙されているのは誰か?―レニエ『女占い師』 ほか)
第2章 「日常生活のなかの美」を求めて(文字を学ぶ子ども―テル・ボルフ『読み方の練習』;日々の営み―ダウ『田舎の料理人の女』または『水を注ぐ女』;母と子の情愛―フェルコリエ1世『授乳する女性』 ほか)
第3章 「ルーヴル美術館の名画」にみるヨーロッパ絵画の仕組み(ヨーロッパ絵画の仕組みと「風俗画」の誕生;ルーヴル美術館、その絶え間なき挑戦;「時のギャラリー」という体験)
著者等紹介
尾崎彰宏[オザキアキヒロ]
1955年福井県生まれ。美術史家。東北大学大学院文学研究科教授。東北大学大学院文学研究科博士課程後期退学(美学・西洋美術史専攻)。専門はネーデルラント美術を中心とした西洋美術史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

![快速マスター中国語 - これ一冊で基礎を固める [テキスト] (新装版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48761/4876154309.jpg)