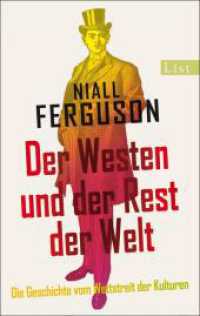出版社内容情報
仕事師時代小説の第一人者が聞き出した名刀匠・河内國平の圧倒的な言葉。その河内親方の信念は「出来る、出来る出来る、出来る出来る出来る、必ず出来る」。世代、職種を超え、心に響くメッセージ。
目次
第1章 仕事はへたがいい(一冊の本が人生を変えた;仕事はへたがいい ほか)
第2章 人間国宝、宮入昭平師からもらった無形の財産(千日の勤行よりも一日の名匠;三年褒めれば駄目になるよ ほか)
第3章 懐の深さ(「決心」と「欠心」;「出来る、出来る、出来る、必ず出来る」 ほか)
第4章 弟子の育て方(物から教わる、人から教わる;若いうちは自己アピールするな ほか)
第5章 故きを温ね新しきを知る(道具は手の延長である;炭切り三年、向鎚五年、沸かし一生 ほか)
著者等紹介
山本兼一[ヤマモトケンイチ]
1956年、京都府生まれ。同志社大学卒。出版社勤務を経て作家に。1999年、『弾正の鷹』で小説NON短編時代小説大賞を受賞。2004年、『火天の城』で松本清張賞を受賞。その後、2009年には『利休にたずねよ』で直木賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ワッピー
36
文京区の日本刀入門講座で薦められて。小説家・山本兼一の聞き書きによる刀匠・河内國平師の軌跡。人間国宝・宮入昭平師と隅谷正峯師の二人の親方について多くのことを学び、それを日々実践しながら、さらに新しい可能性に挑戦し続ける河内氏の言葉には多くの含蓄があります。刀を鍛造する日々の作業での気づき、人の育て方、マインドセット、効率の重要さのような現在でも通用すること、あるいは逆に今となっては激減している職人という存在の難しさもまた伝わってきます。日本刀鍛造のプロセスを知るにも、また刀匠の哲学を知るにもおススメ。2023/01/28
鉄骨構造
11
刀鍛冶、河内國平親方の話。叩き上げの職人の話。彼らの生きる世界では、残業が多いとか、休みが少ないとか、理不尽なことを言われたとか、そういう主張は全く通用しない。現代人の考え方にはそぐわない部分もあるけれど、仕事にはやはりある程度の厳しさが必要だと改めて思った。何百年もかけて伝わってきたこと。故きを温ね新しきを知る、か。現代人にとって、その価値とは? 美術品・伝統工芸品としての価値は非常に高いと思うが、その伝承と発展を担ってきた職人さんたちから学ぶべきことも多いと思う。2018/11/10
なつきネコ@吠えてます
6
刀匠の家系に産まれた河内國平氏のエッセイ集みたいな感じ。鉄の変化を見続け、刀を作る執念には脱帽。人間の生き方として尊敬する。しかし、國平氏も昔は弟子の中でも一番に不器用。そんな國平氏だから仕事は下手がいい、の言葉は納得。器用な人間はすぐにでき、努力しないため大成はしない。しかし、今の社会は器用に渡り歩ける社員を大事にする。私が作る物は私の分身だが、お金の為に雇われ作った物の中には私はいない、マルクスの疎外革命論を思いだした。宮入昭平氏の時代は國平氏がいたが、國平氏の時代には誰がいる?日本刀の将来が心配だ。2017/01/04
さくら餅
4
刀匠・河内國平氏のエッセイ本。刀匠という縁のない職業に物珍しさを感じながら読みましたが、人生の教訓にしたくなるような言葉が沢山ちりばめられていました。特に「仕事はへたがいい」「決心は自分の心で決めること。他人の言葉や考えに影響を受けるのは決心ではなく欠心だ」が心に残りました。河内氏の刀への情熱は尊敬に値します。2017/01/16
みっくん
2
刀匠のエッセイみたいなものでした。 鉄は熱いうちに打て、というのが短期に教えることも差すのだろうと言う洞察に納得。2016/10/28