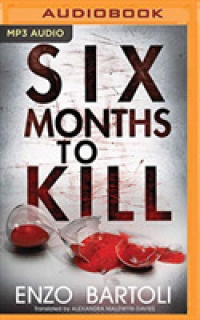出版社内容情報
混迷を極める中東情勢。その中で唯一民主主義を実現した国、トルコ。トルコを知ることで、中東の未来が見えてくる。著者は中東研究、イスラム系移民の研究者として日本では第一人者である。
内容説明
混迷を極める中東最悪のシナリオを回避できる唯一の国はトルコである!日本における中東国際政治の第一人者が書き下ろす、トルコ、そして中東。
目次
はじめに いまなぜ、トルコか
第1章 トルコの近代化と脱イスラム
第2章 トルコの再イスラム化
第3章 ヒズメト運動
第4章 トルコと西欧諸国の関係
第5章 トルコと周辺諸国の関係
著者等紹介
内藤正典[ナイトウマサノリ]
1956年東京都生まれ。東京大学教養学部教養学科科学史・科学哲学分科卒業。博士(社会学)。専門は多文化共生論、現代イスラム地域研究。一橋大学教授を経て、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
60
先日の大統領選挙を踏まえて、手に取った一冊。国体の成り立ちと背景を踏まえた現在の立ち位置が、簡潔にまとめられている。近代国家復権の祖・ケマル氏の哲学。現実主義と民族問題に、拍車をかける神上位。西欧化の呪縛も、国家原則。国家と国民の利益が前提、という一貫性。思い通りにならないUS/EUは、苦虫をかみ潰したような気持ちかと推察。一方、日本の政治家もこの一貫性は一考の価値がある気がする。 2018/07/29
みねたか
22
1990年代から現在までのトルコの歩みがよくわかる良書。厳格な政教分離からイスラム的公正の価値観を打ち出した緩やかなイスラム化の歩みは成功しつつあるようだ。湾岸戦争以降の中東世界の混乱のなか、世界の架け橋を担いうるこの国の重要性はますます高まっていくだろう。折しもISによるテロで多くの犠牲がでるなど難しい対応を迫られているが、2023年建国100年の時にトルコがムスリムと非ムスリムの希望の国となっていることを願うという著者の思いに強く共感。2017/01/03
ntahima
17
【県図23】懐かしき母校の先生であるという身贔屓がゼロとは言えないが、中東、特にトルコに関しては一番信頼の置ける研究者。著作も勿論為になるが、講演動画などを見ると専門性に裏付けられた客観性と情熱的な語りが印象的。日本でエルドアン大統領というと保守の剛腕政治家という印象しかないが本書を読むと印象が変わる。勿論、二元論の善玉とはとても言えないが、自分の立ち位置を少しばかりずらすと全く別の世界が見えてくる。『欧州諸国対ムスリム社会、もう一つスンニ派対シーア派、そしてもうひとつは、世俗的な政権対イスラム主義勢力』2017/03/24
黒猫
17
トルコは泰然自若。臨機応変。これが読後の感想です。日本において、トルコはアジアとヨーロッパの中間でどっち?とか、料理がおいしいとか、ヘレニズム文化だとか、そんな程度。中東イスラム圏とくくられることもしばしばある。この本は、トルコの国際的立場、国内外の問題の所在を示すと共に、建国時からの政教分離政策。国民を守る場合においては、軍事力を行使するという一貫した立場。トルコ、イスラム国、欧米としたたかに渡り合う外交術。移民問題。様々な問題を抱えながらも欧米に頼られる理由がわかる。良書です。2016/03/12
BLACK無糖好き
15
昨年の秋頃、BSフジ「プライムニュース」でシリア難民問題を取り上げた時に出演していた著者が、番組終了間際に、中東一帯のムスリムに強い影響力を与え得る人物としてトルコのエルドアン大統領の名前を挙げていた事が強く印象に残っている。恐らく本書を執筆し終わる時期だったのではと推察する。本書はトルコ共和国の成り立ちからその独特の国家運営制度、ヨーロッパや中東アラブとの関係などが非常に分かりやすく書かれており、混乱を極める中東情勢の理解を深めるのにも大いに役立った。同時に政教分離の難しさも改めて感じた。2016/05/03