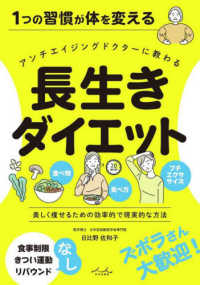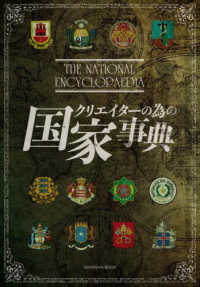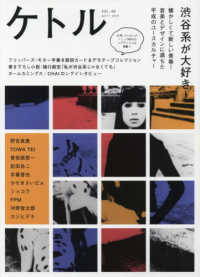出版社内容情報
「故郷」という日本語をぼくは知らなかった。だがここには、確実にぼくの家があった──。半世紀ぶりに故郷・台湾を訪れる〈時〉の旅人の物語。新境地を開く8年ぶりの小説。
内容説明
「故郷」という日本語をぼくは知らなかった。だがここには、確実にぼくの家があった。52年ぶりの「ぼくの家」。新境地を開く8年ぶりの最新小説。
著者等紹介
リービ英雄[リービヒデオ]
作家・法政大学国際文化学部教授。1950年、カリフォルニア生まれ。少年時代を台湾、香港で過ごす。プリンストン大学とスタンフォード大学で日本文学の教鞭を執った。『万葉集』の英訳により全米図書賞を受賞。89年から日本に定住。87年、「群像」に「星条旗の聞こえない部屋」を発表し小説家としてデビュー。92年に作品集『星条旗の聞こえない部屋』で野間文芸新人賞を受賞し、西洋人として初めての日本文学作家として注目を浴びる。『千々にくだけて』で大佛次郎賞、『仮の水』で伊藤整文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
78
現在も続くかのようなアイデンティティの模索と、故郷/桃源郷という2つの「郷」の回想。河南省の奥地で探し求める”自分の”台湾の幻影。50年ぶりの台中訪問も同様。家が在った場所で母を想い、溢れる涙。国共内戦を経た大陸から台湾への逃避行、台中での閉じられた世界での異教徒家族で生活など、葛藤の数々は私には想像もできない。印象的なのが、心底に何かを呼び起こした”万葉集の英訳”の件。古語に垣間見る歴史と文学。文字の成せる業ではなかろうか。Going Native、突き詰めれば、最後はやはり「心」だと信じたい。2020/03/07
三柴ゆよし
18
台湾にある「日本人建的」日本式家屋に生まれ育ったユダヤ系アメリカ人が、日本語とそれによって紡がれた文学に魅せられ、やがては自らも日本語の文学を生み出してゆく。長じてのち、彼は自らの記憶の光景をもとめて大陸の奥地に、そしてついには現代の記憶の場所を訪うことになる。本書はリービ英雄という物語のルーツともいうべき小説集である。リービとともに台湾、中国大陸、そして日本の現代を歩き、その軌道に沿うて思考することで、彼にとっての文学というのだけでなしに、日本近代文学のひとつの起源がひらかれてゆくような感覚をおぼえた。2016/04/20
メセニ
10
自分は何者で、故郷とは何か。作家はアメリカに生まれ、幼少期を台湾で過ごす。宣教師学校ではジェームズ王版の聖書を朗読し、家の外からは現地の言葉が聞こえる。統治時代からあるその家は「日本的」な面影を漂わせる。やがて日本語で書く作家となるが、彼は常に自己の同一性や言葉の問題と直面してきた。彼の文章には独特の”うねり”がある。それは幼少期のねじれた環境が生んだ視点と思考なのだろうか。原風景を求め、半世紀ぶりに”模範郷”を訪れた「ぼく」は、そこで何を見たか。彼の紡ぐ文体、言葉の結晶がリービ英雄という人そのもである。2017/02/19
Lila Eule
10
台湾、大日本帝国、中華民国、中華人民共和国、台湾語、日本語、英語と、異次元の文化が、時代を超えて折り重ねられていく不思議な旅行記だ。さまよう自身の姿が、日本家屋の鈍い色あいに溶け込んでゆくような不思議な文章だ。修飾文の重なり合いを理解するのに読み返すところがあるが、味わい深い文章だ。西洋人初の日本文学者と著者略歴があったが、八雲はどうなるのだろう。2016/07/22
ひろみ
6
『もし「ゴーイング・ネイティブ」が本当にあるとすれば、それは本来の「ネイティブ」たちが創り上げた言葉の中に自らの新しい生命を求めることである。人種でも生い立ちでもなく、文体の問題なのである。』2016/06/29