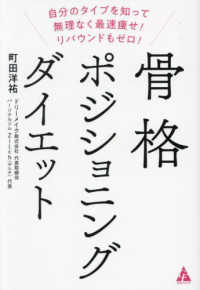出版社内容情報
奈良時代。父・藤原不比等(ふじわらのふひと)から「闇を払う光となれ」と光明子(こうみょうし)の名を授かった一人の少女は、やがて聖武天皇の妃に。女として、母として、皇后として、苦難の日々を凜と歩んだ生涯に魅せられる歴史長編。
内容説明
父・藤原不比等の願いが込められたその名を胸に、一人の少女が歩みだす。朝廷の権力争い、相次ぐ災害や疫病…。混迷を乗り越え、夫・聖武天皇を支えて国と民を照らす大仏の建立を目指す。光明皇后、その生涯が鮮やかに蘇る渾身の歴史長編。
著者等紹介
葉室麟[ハムロリン]
1951年北九州市小倉生まれ。西南学院大学卒業後、地方紙記者などを経て、2005年『乾山晩愁』で歴史文学賞を受賞し、デビュー。2007年『銀漢の賦』で松本清張賞、2012年『蜩ノ記』で直木賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
265
光明皇后を描いた物語である。 天平時代を背景に、 日本の絵巻が現代に蘇る。 藤原不比等の娘として生まれ、聖武天皇に 嫁ぎ、権謀術数渦巻く中、日本の天平文化を 開花させた生き様はひどく清冽で清々しい。 日本史の教科書でしか 出てこない人々が 著者の筆力で蘇る..改めて 歴史小説の 楽しさを実感する、そんな本だった。2017/03/02
藤枝梅安
94
聖武天皇の皇后・光明子を描いた作品。奥山景布子さんの「キサキの大仏」と同じ題材を扱っているが、「キサキの大仏」は夫婦愛と母娘の確執というホームドラマ。この作品では若き日の道鏡・玄昉・吉備真備なども登場し、長屋王の息子・膳夫(かしわで)との心の交流や、長屋王の変に至る過程も扱われ、「政争に巻き込まれないよう苦慮する天皇と皇后」という視点で、大仏建立までを物語る。この作品でも聖武天皇は優柔不断な人物として描かれている点が興味深い。大仏を作るために多くの人命が失われ、民が疲弊した点を描いた「国銅」には及ばない。2014/10/06
それいゆ
79
奈良時代の歴史学習をした感じです。登場人物の名前の読み方が難解で、歴史小説なので結末も分かっており、途中で何度も挫折しそうでしたが、何とか読了しました。思っていた以上に女帝が多くて、現在の皇位継承論争は何なんだろうか?という気もしてきました。この作品は、光明皇后の話というよりも「長屋王の変」を小説にしたものなんですね。単語でしか知らなかった歴史の出来事を初めて理解することができました。いつも思うのですが、葉室さんにはこの手の小説は似合いません。「蜩ノ記」のような傑作の創作時代劇を期待しています。2014/10/11
starbro
62
女性が主役でも大きく政治が動いた時代の物語。古の奈良時代に浪漫飛行出来ます。いつの間にか、女性は天皇に即位できなくなっていますが、時の権力者に天皇制は色々とゆがめられて来たんでしょうね!2014/11/21
ちゃんみー
60
昔『天上の虹』(里中満智子)『日出処の天子』(山岸凉子)を読んでからというもの、この時代の人物に惹かれていました。(中高生の時は全然興味なかったんですけど(^^;;)葉室さんが描く光明皇后はどんなんだろうと思い読んでみました。持統、元明、元正と引き継がれてきた女帝時代。そしてこの主人公の光明子(光明皇后)。いつの時代も女性が強かったんだな、と思います。今まで以上にこの時代に惚れ込みました。高市皇子の子供、長屋王とその子膳夫の死。奈良の大仏を建立した本当の理由は長屋王の祟りを鎮めるためだったわけね。2014/10/02
-

- 電子書籍
- 【デジタル限定】桜りん写真集「開脚ガー…