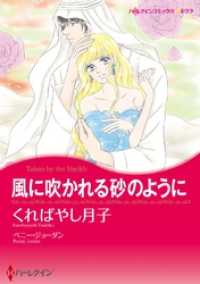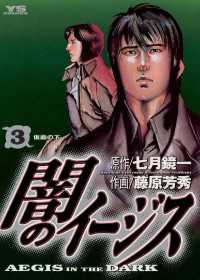内容説明
ニュージーランドにあるチェアマン寄宿学校の生徒たちは、夏休みを利用した6週間の沿岸航海を楽しみにしていた。出発前夜、早くも乗船した少年たちだったが、船は、ふとしたことから漂流を始める。嵐に流され、絶海の孤島に上陸した、8歳から14歳までの15人の少年たち、彼らの思いもしなかった「二年間のバカンス」が始まる。
著者等紹介
ヴェルヌ,ジュール[ヴェルヌ,ジュール][Verne,Jules Gabriel]
1828‐1905。フランス西部のナントに生まれる。空想科学小説の父。子供のころから冒険小説や旅行記を読みふけり、未知の世界に憧れる。少年時代の夢に、地理学、物理学等の新しい知見を盛りこんだ『気球に乗って五週間』によって、たちまち流行作家となる。以後、小説『驚異の旅』シリーズ80余編を発表。今なお、古典的名作として世界中で読み継がれている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。