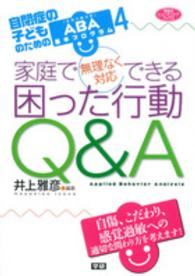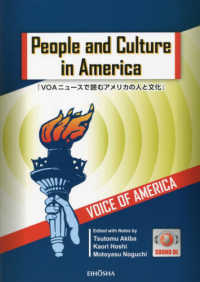内容説明
万葉集は、古代日本人がつづったその魂の燃焼の譜である。美しいものをしんじつ、美しいと見る眼、美しいと感じる心とは、どういうものかを、万葉集によって探りあてた著者。4516首の歌から、300首、恋の歌、子を想う親の歌、防人とその妻たちの歌、ユーモラスな歌、酒の歌、女の歌…などに分類。独自の解釈で、旋律の美しさと、万葉びとのよろこびと嘆きを伝える。索引付き。
目次
恋の歌
親と子の歌
酒の歌
女ごころ・男ごころの歌
ますらをの歌
挽歌
旅の歌
ユーモラスな歌
七夕の歌
防人とその妻の歌
雪、月、雨、花と鳥の歌
貧窮と無常と奴隷の歌
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
i-CHIHIRO
1
お気に入りレベル★★★★☆2018/07/01
半べえ (やればできる子)
0
★★★2011/02/08
fukurou3
0
万葉集は庶民から天皇まで歌というが庶民は本物?小学校も寺子屋もない時代に字が書けた?書ける人の前で詠んだ?即興は難しいからずっと歌い継がれてた?それとも庶民のふりをして詠まれた?東女の歌とかはプロ作詞家による水商売の女性の気持ちを男性歌手が歌った昭和歌謡みたいなものでは?防人歌は?太平洋戦争中に勇ましい歌しか教えなかったように、白村江戦当時、消極的な歌は許されるとは思えないが、反戦(反天智)のプロパガンダ?あと、石川郎女の「我が聞し」の歌の「足」は万葉の大らかさで、別の器官と解釈した方がしっくりくる。2022/07/14