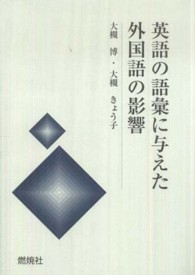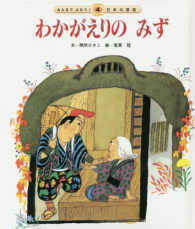内容説明
国際的な免疫学者であり、能の創作や美術への造詣の深さでも知られた著者。01年に脳梗塞で倒れ、右半身麻痺や言語障害が残った。だが、強靭な精神で、深い絶望の淵から這い上がる。リハビリを続け、真剣に意識的に生きるうち、昔の自分の回復ではなく、内なる「新しい人」の目覚めを実感。充実した人生の輝きを放つ見事な再生を、全身全霊で綴った壮絶な闘病記と日々の思索。第7回小林秀雄賞受賞作。
目次
1 寡黙なる巨人
2 新しい人の目覚め(生きる;考える;暮らす;楽しむ)
憂しと見し世ぞ―跋に代えて
著者等紹介
多田富雄[タダトミオ]
1934年生まれ。東京大学名誉教授。免疫学者。95年、国際免疫学会連合会長。抑制T細胞を発見。野口英世記念医学賞等内外多数の賞を受賞。2001年、脳梗塞で倒れ声を失い、右半身不随となるが、リハビリを行いながら著作活動を続ける。能楽にも造詣が深く「望恨歌」など新作能の作者としても知られる。『寡黙なる巨人』で08年第7回小林秀雄賞受賞。10年4月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うりぼう
86
失われた機能は、元には戻らない。新たな回路が繋がり筋肉が動き出す。それは、あたかも自分の中に鈍重な巨人が生まれるかのよう。人は生まれて、何億年の生命の摂理により、当り前のように動き出す。でも、本当は自分に中に俊敏な巨人を生み出すのだ。多田氏は、その追体験。竹内敏晴氏が、声を産んだように。野口三千三氏が、原初生命体の身体を探求したように。キューブラー・ロスの臨死体験を超え、より生命として生きることを実感する。神は氏に、リハビリの重要性を訴えることと、能を通じて戦争と生命を伝える使命を与えたのか。心から合掌。2010/08/25
さきん
28
脳梗塞をきっかけに死と生と身体と向き合うことになった免疫系の研究をしている学者。闘病生活の中で、趣味である能、狂言の言葉や詩が出てくる。ある程度回復後は、経験を通じて感じた医療、リハビリの問題に取り組む。医師、看護師他にリハビリの専門家や退院後のサポートの充実が課題だということがよくわかる。しかし、老年人口増大の影響で、社会保障費が増大しており、財政が苦しくなっている厚労省のつらさもまたよくわかる。2017/01/31
mari
20
東大名誉教授の免疫学者である著者が、突然脳梗塞で倒れ、死の淵から生還したが、右半身の自由を失い、喉の麻痺のため、発声も食事も出来ない。その苦悩と苦痛と(嚥下出来ないと、ここまで苦しいとはじめて知りました)リハビリでの医療の問題点などを文章にされた、息詰まる迫力のある内容です。2014/08/27
ホークス
18
67才で脳梗塞による右半身不随となった著者。「巨人」とは、異様に重く動かない右半身を指す。東大名誉教授の免疫学者で文筆家でもある事が、墜落した落差の大きさと、事態を冷徹に見据えるしかない苛酷さを示す。話す事も歩く事もできず、食事は死と紙一重の苦行。だが著者は明晰さだけは残された事に感謝し、リハビリに耐え、思索を深める。それが唯一の人格崩壊を防ぐ手段なのだ。その姿に驚嘆しながらも、だからこそ、その必死の思考に対して安易に共感せず、「常に自分の信念を再構築する勇気を持つ」事で著者に報いたいと思う。2016/09/04
mayld
7
多田さんを知ったのはこの本にも収録されている「リハビリ中止は死の宣告」が朝日新聞に載ったときからでした。だから彼を知り、彼の著作を読んでファンになったのはほんの数年前。もっと早くお会いしたかった。多田先生のおかげで能楽堂に通うようになったし、現在の日本の福祉環境の遅れにも目を向けるようになりました。一度も会ったことはないけれど先生は私の恩師です。2010/10/06