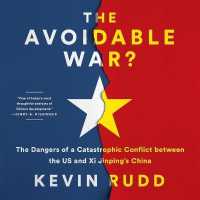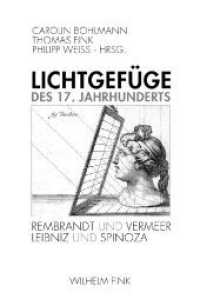内容説明
1942年、フランス。親衛隊所属となり過酷な戦いを強いられてきたカールは、束の間の休息を得ていた。一方、ヘルマンはソ連軍に捕らえられ捕虜として屈辱の毎日を送っていた。それでも「戦争」は続く。「ヒトラー・ユーゲント」の時代を生きた男たちの、心の軌跡をたどり、運命に翻弄されゆく姿を描く長編ここに完結。
著者等紹介
皆川博子[ミナガワヒロコ]
1930年1月2日生まれ。東京女子大中退。85年「壁―旅芝居殺人事件」で日本推理作家協会賞、86年「恋紅」で直木賞、90年「薔薇忌」で柴田錬三郎賞、98年「死の泉」で吉川英治文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ヨーイチ
39
「総統の子達」の物語も終幕を迎える。軍人として厳しい自己抑制と訓練を続けて来た主人公達の運命が、どう転んでも悲惨な物にならざるを得ない為、本当に読み進めるのが辛かった。矛盾と絶望に囲まれた主人公達に作者が「悟り」の様な心境を語らせるのは、作者の慈愛のような気がする。同盟を結び、同じ様に敗北した国に生を受けた者として、戦後処理とか飢餓、喪失感は共通する所もあるのだが、軽々しく断定は控えるべきだろう。歴史は物語だとすると、ソビエトが健在な頃は、こんな物語を発表出来たかどうか。続く2016/03/21
不羈
33
第二次世界大戦のナチスドイツの軍隊=悪、そしてその存在自体がタブー的な現代と感じるけれどそんな通り一遍の考えを覆してくれる。ユダヤ人の虐殺もきっちり書いているが、ソ連の軍隊、連合国、パルチザンが行った行為についてもドイツSS陸軍を通した目線で描写してくれている。全てが善/悪の二元論では切り分けられないと改めて気づきを与えてくれた。 読むことができて良かった。この本は、そういう著作。 2014/12/31
Hugo Grove
20
勝てば官軍。現実は決して平等ではない。あの時代ドイツで生まれた子どもたちにとっては誇りを持って戦争に出て行ったのだ。戦争はあまりにも残酷で非情だ。戦争を知らない私達世代は戦勝国側だけの不公平な歴史を植え付けられた。しかし私は長崎出身で子供の頃から納得いかなかった。なぜ原子爆弾を広島長崎に落としたのか?あれを無差別殺戮と呼ばずして何を殺戮と呼ぶのか。作中の若者が死なない戦争はないですからとまだ14−15にしかならない少年の言葉が胸に突き刺さる。勝っても負けても若者は死ぬんです。戦争は愚かなことです。素晴しい2013/01/16
Lumi
19
読了してから色々な感情が渦巻いて、言葉にならなかった。数日経ち、やっと感想を書いている。 これまではナチスは全て、兵士も含めて恐ろしい思想を持つ悪だと思っていた。しかし、今作の青年兵士の目線を通して、一人一人はただ国のために戦っていたんだと気づいた。そして、ナチスだけでなく他の国も残酷なことをしていたのだと知った。敗戦国が悪で、勝った国の非道な行いは無かったことになる。戦争はどの国も自国の正義を振りかざし戦うかもしれないが、その「正義」とはなんなのか?と考えさせられた。戦争に正義なんてないのだと思う。2018/11/24
おぎにゃん
16
「犯罪人。この上なく忌まわしい言葉。正々堂々と、力ある限り戦った。それを、犯罪と呼ぶのか」…総統と帝国を信じて武装SSに志願して戦っただけなのに、戦勝国の思惑で、戦後処刑されていった純真で勇敢な若者たち…あまりにも悲しすぎる。総統と帝国は「悪」だとしても、信じた者全てを「悪」と断罪することはできるのだろうか…柄にもなく、そんな事を深く考えこんでしまった。臨場感が物凄い、心にズシーンと来る名作です。2013/11/13
-

- 和書
- 時代を勝ち抜く人材採用