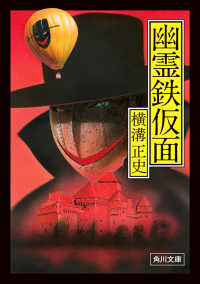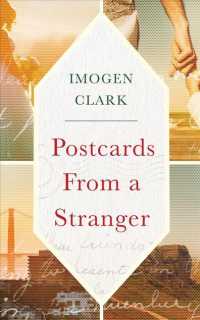出版社内容情報
共同通信社が配信するウェブ「47NEWS」でオンライン記事を作成し、これまで300万以上のPVを数々叩き出してきた著者が、アナログの紙面とはまったく異なるデジタル時代の文章術を指南する。
これは報道記者だけではなく、オンラインで文章を発表するあらゆる書き手にとって有用なノウハウであり、記事事例をふんだんに使って解説する。
また、これまでの試行錯誤と結果を出していくプロセスを伝えながら、ネット時代における新聞をはじめとしたジャーナリズムの生き残り方までを考察していく一冊。
◆目次◆
第1章 新聞が「最も優れた書き方」と信じていた記者時代
第2章 新聞スタイルの限界
第3章 デジタル記事の書き方
第4章 説明文からストーリーへ――読者が変われば伝え方も変わる
第5章 メディア離れが進むと社会はどうなる?
◆著者略歴◆
斉藤友彦(さいとう ともひこ)
共同通信社デジタル事業部担当部長。
1972年生まれ。
名古屋大学文学部卒業後、1996年共同通信社入社。
社会部記者、福岡編集部次長(デスク)を経て2016年から社会部次長、2021年からデジタルコンテンツ部担当部長として「47NEWS」の長文記事「47リポーターズ」を配信。
2024年5月から現職。著書に『和牛詐欺 人を騙す犯罪はなぜなくならないのか』(講談社)がある。
内容説明
共同通信社が配信するウェブ「47NEWS」でオンライン記事を作成し、これまで三〇〇万以上のPVを数々叩き出してきた著者が、アナログの紙面とはまったく異なるデジタル時代の文章術を指南する。これは報道記者だけではなく、オンラインで文章を発表するあらゆる書き手にとって有用なノウハウであり、記事事例をふんだんに使って解説する。また、これまでの試行錯誤と結果を出していくプロセスを伝えながら、ネット時代における新聞をはじめとしたジャーナリズムの生き残り方までを考察していく一冊。
目次
第1章 新聞が「最も優れた書き方」と信じていた記者時代(基本の形「逆三角形」;リードさえ書ければ何とかなる ほか)
第2章 新聞スタイルの限界(当初は原稿に手をあまり加えなかったが…;PVを稼げないのはなぜ? ほか)
第3章 デジタル記事の書き方(読者にストレスを与えない;ストーリーが共感を呼ぶ ほか)
第4章 説明文からストーリーへ―読者が変われば伝え方も変わる(読者を迷子にしない;説明文は読みたくない ほか)
第5章 メディア離れが進むと社会はどうなる?(新規の読者が増えない文体;目立つ「コピペ」、多用される比喩 ほか)
著者等紹介
斉藤友彦[サイトウトモヒコ]
共同通信社デジタル事業部担当部長。1972年生まれ。名古屋大学文学部卒業後、1996年共同通信社入社。社会部記者、福岡編集部次長(デスク)を経て2016年から社会部次長、2021年からデジタルコンテンツ部担当部長として「47NEWS」の長文記事「47リポーターズ」を配信。2024年5月から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
テイネハイランド
Rie【顔姫 ξ(✿ ❛‿❛)ξ】
Eric
ATS