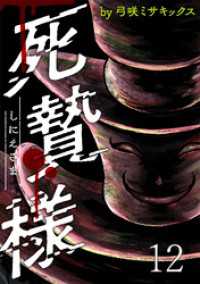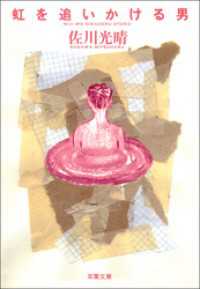内容説明
推古以来、飛鳥朝から奈良朝にかけて、六人の女帝たちが誕生した。これほど多くの女帝たちが集中して登場した時代は、世界史的にみても例がない。女帝が役割を終えるのは、平安初期に皇太子制度が整備されたことによるが、女帝はどうしてわが国に、それも古代に集中して登場したのか。皇位継承の中で果たした女帝の役割は、何だったのか。元明天皇即位の詔に出てくる「不改常典」という言葉に隠された、真の意味とは?本書は、女性天皇という存在に光を当てることで、古代の王権の知られざる相貌を浮き彫りにする。皇位継承のルールを解き明かした、新たな古代日本史。
目次
第1章 嗣位すでに空し(穴穂部皇子の反乱;女帝の「ワカミタフリ」 ほか)
第2章 皇位継承法を変えた女帝(吉野の盟約;称制の女帝 ほか)
第3章 女帝幻想(悲しき女性皇太子;呪縛された女帝 ほか)
終章 女帝とは何だったのか(女帝の係累;女帝と斎王 ほか)
資料編
著者等紹介
滝浪貞子[タキナミサダコ]
1947年大阪府生まれ。1973年京都女子大学大学院修士課程修了。京都女子大学文学部教授。文学博士。専門は古代日本史。NHK講座「歴史で見る日本」で飛鳥~平安時代を担当(1989年~94年)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。