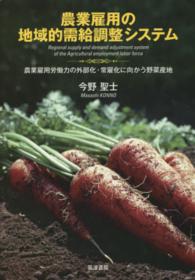内容説明
蒙古襲来以後、東アジアの情勢は緊迫の度を加えていた。後醍醐天皇の討幕計画は、大覚寺統と持明院統の皇統争いを巻き起こし、南北潮の動乱が始まった。新田義貞らの活躍により鎌倉幕府は滅亡するが、誕生した建武政権は順風満帆ではなかった。天皇と足利尊氏の対立が高まり、動乱はさらに大きな輪となって時代を包みこんでゆく。―南北朝動乱100年の転換の諸相を、鮮やかにとらえる。
目次
はじめに 太平記の時代
第1章 東アジアの中の日本
第2章 日本の境界と周縁
第3章 専制と親政の世
第4章 漂泊民と異形の群像
第5章 未完の封建王政
第6章 崩れゆく新政権
第7章 兄弟相はむ尊氏と直義
第8章 動乱の主役たち
第9章 動乱の狭間で生きる人々
第10章 動乱終息へ
おわりに 動乱の終焉
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
49
#解説歌 蝦夷琉球周辺文化と亜細亜での動き重なる歴史同型2016/08/23
いきもの
3
霜月騒動から足利義満が表舞台に出てくるぐらいまでの歴史についての本。元弘の乱や観応の擾乱などの合戦の歴史は勿論のこと、この時代の政治体制や経済、文化、民衆の暮らしなども概説。むしろ合戦の戦術面などに関してはやや不足気味にも感じられる。元や高句麗など周辺国との関連や、東シナ海、オホーツク、日本海経済圏などの流通の話、この時代の蝦夷/アイヌの発展や、権力者に対する民衆の抵抗や民衆同士の争いなど興味深いものが色々あった。特に犯罪を犯した犯人が不明な場合匿名の投票で決めるとか思わず笑ってしまった。2014/07/24
陽香
2
199201112016/10/25