内容説明
都市のライフラインが遮断されたとたん、コンビニやスーパーの棚は瞬時に空っぽになり、食品不足の街には異様な緊張感が満ちる…。3.11東日本大震災を体験した著者が説く、イザというときに命をつなぐ食事学。
目次
第1章 私の東日本大震災の経験―地震後の1カ月間に感じていたこと
第2章 これまでの震災から学ぶ教訓―震災時の「食」から見えてくるもの
第3章 大震災を生き抜くための「食」とは?―震災前の心構えと備蓄食の条件
第4章 では、何をどう「常備蓄」しておけば安心か―食料、水、熱源は自分で備える
第5章 震災と、どうつきあっていくか?―「地震の国」のにんげんだもの
第6章 福島原発事故と放射性物質―リスクと安全にどう向き合えばよいか?
著者等紹介
石川伸一[イシカワシンイチ]
1973年福島県生まれ。東北大学農学部卒業、同大学院農学研究科修了。北里大学助手・講師、カナダ・ゲルフ大学客員研究員を経て、宮城大学食産業学部准教授。専門は分子レベルの食品学・栄養学。主な研究テーマは、鶏卵の栄養性、機能性に関することなど(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
aisapia
12
水は1日1人3リットル、ガスボンベは1日2本と思って備蓄する。普段食べているものをローリングストック。甘いものは必ず欲しくなる。トイレが大事。悲惨な状況が最初の写真のページからとても伝わってきた。電子マネーが増えている今、現金を持たないと停電したら何も買えない。そして東京なら絶対暴動がおきるだろうな…恐ろしい。備蓄をさらに強化しようと思った。2023/01/24
ほっそ
7
著者は大学の先生で、仙台在住の方。私と同じ、津波被害のなかった宮城県民です。この本を読んで、普段私が取り組んでいたことが、間違っていなかったのだということ、確信しました。「普段食べているものを、備蓄する」ってこと。さらにこの本を参考にして、実践していきたい。また、必ず宮城県沖地震が来ると思ってたので、心は「全壊」しなかった。これも納得。 2012/04/09
tan_keikei
4
仙台で東日本大震災を経験した食品学・栄養学の研究者による、災害時の食にフォーカスをあてた本です。防災本は語り口がこわいものが多いのですが、これはユーモアをまじえた柔らかい文体なので読みやすくスッと頭に入ってきます。食についてのエピソードで、缶のコーンポタージュと震災二日後に店を開けたケーキ屋さんが印象に残りました。震災を経験した著者による「常備蓄」や栄養学の観点からの震災時の食に関する提言は大変ためになるものだと思います。おすすめです。2013/02/03
ミュンヘン
3
食品研究者としての真摯で率直な語り口と奥様の優しい絵とあいまって、語りかけられるように素直に読める本。甘さとカロリーを人は求め、ミネラルとビタミンを身体は訴求する。人は「落差」に傷つくことや「安全に排泄できる」ことがどれほど重要か、普段の物流は「動的均衡」、常に誰かの手が入ってこそ保たれていると言うこと。乾麺、パスタ、好みの缶詰、乾物、レトルト、フリーズドライ。水が少なくても、お湯がなくても食べられるもの。そして自分のためだけでなく、周りの人をも救うために。2013/03/12
まこっぴ
3
昨年の大震災を教訓として災害時の備えを見直した方も多いと思います。この本では、ご自身が被災され震災後の厳しい状況を経験された、宮城大学の石川伸一准教授が、食事を中心にどんな備えをしておけばいいかをわかりやすく解説しています。ライフラインが絶たれ、精神的にも肉体的にも追い詰められるなか、やはり人を支えるものは”食”であるということがよくわかりました。大震災から1年以上経ち、次第に危機意識が薄れていくなか、もう一度”その時”に備えるためにモノもキモチもきちんと見直してみたいと思いました。2012/06/08
-
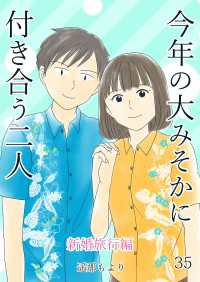
- 電子書籍
- 今年の大みそかに付き合う二人【単話版】…
-
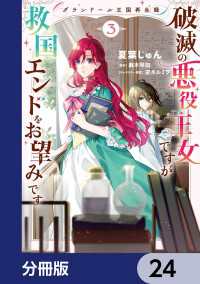
- 電子書籍
- グランドール王国再生録 破滅の悪役王女…
-
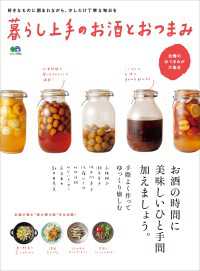
- 電子書籍
- 暮らし上手のお酒とおつまみ
-
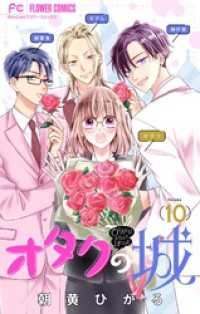
- 電子書籍
- オタクの城【マイクロ】(10) フラワ…
-

- 電子書籍
- 僕の可愛い婚約者の為ならば。17 素敵…




