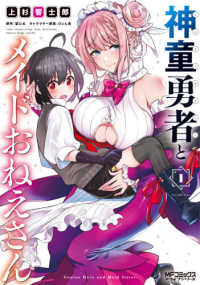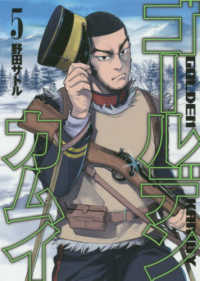出版社内容情報
茶席の床の間でよく使われる禅語は難解な意味のものが多い。本書はその禅語をできるだけわかりやすく解説し、人生論として読んでも実に面白い内容となっている。
本書は、かつて好評を博した「よくわかる茶席の禅語1・2」(主婦の友社刊)にあらたに増補追加を加え決定版としたものである。「無」「喝」など一字の禅語から、「春色無高下花枝自短長」など十字の禅語まで語数順に並べ、だいたい茶席で使われる禅語はほぼ網羅してある。一般的に禅語は難解とされ、難しい解説書が多いが、本書はとにかくわかりやすく、しかも面白く解説してあるので、人生論として読んでも楽しめる。著者の有馬頼底氏は臨済宗相国寺派管長で、禅語に関する著作も多く、現代の禅語の第一人者である。
目次
一字(無;○(円相) ほか)
二字(当機;悟道 ほか)
三字(惺々著;莫妄想 ほか)
四字(処々全真;随処作主・立処皆真 ほか)
五字(彩鳳舞丹霄;松無古今色・竹有上下節 ほか)
六字(処々円光独露;明歴々露堂々 ほか)
七字(三級浪高魚化龍;桃花依旧笑春風 ほか)
八字(頭上漫々脚下漫々;応無所住而生其心 ほか)
十字(一片月生海幾家人上楼;十年帰不得忘却来時道 ほか)
著者等紹介
有馬頼底[アリマライテイ]
昭和8年、東京に生まれる。16年、大分県日田市臨済宗岳林寺にて得度。30年、京都臨済宗相国寺僧堂に掛塔(入門)、大津櫪堂老師に師事。43年、師の後を受けて相国寺塔頭大光明寺の住職となる。46年、相国寺派教学部長に就任。56年、三重県津市の社会福祉法人敬愛会理事長に就任、現在に至る。59年、相国寺承天閣美術館設立により事務局長に就任。平成7年、同館長に就任、現在に至る。昭和63年、京都仏教会理事長に就任、現在に至る。平成7年、臨済宗相国寺派7代管長(相国寺132世)に就任、同時に鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)の住職も兼ねる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
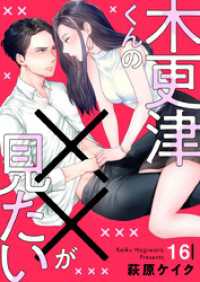
- 電子書籍
- 木更津くんの××が見たい16 comi…
-
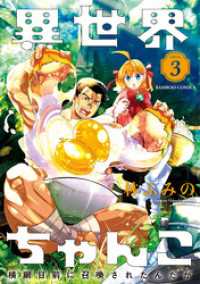
- 電子書籍
- 異世界ちゃんこ 横綱目前に召喚されたん…