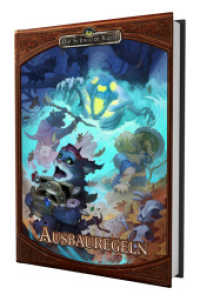内容説明
「自由」と「平等」がともには実現できないとき、私たちはどちらを優先させるべきなのだろうか?フランス革命の渦中にあって、行政府がおのずから担ってしまう専制的な体質をいち早く指摘し、草創期のアメリカに健全な民主主義と自由の実現を見た、トクヴィルの思想の全貌。『アメリカの民主主義』(第1巻・1835年/第2巻・1840年)と『旧体制と大革命』(第1巻・1856年/第2巻・未完)、および膨大な書簡群を読み解きながら、地方自治、陪審、アソシアシオンを「民主主義の三つの学校」と位置づける。冷戦の終結、社会主義の崩壊ののち、その先見性がおおいに再評価された大思想家の思索像。
目次
第1章 民主主義を見る新しい視座
第2章 後見的権力と政府依存症
第3章 地方自治―自由の小学校
第4章 陪審―法的精神の学校
第5章 アソシアシオン―共同精神の学校
第6章 トクヴィルの現代性
著者等紹介
小山勉[オヤマツトム]
1936年、鹿児島県生まれ。早稲田大学政経学部卒業。同大学院政治学研究科修士課程修了。東京都立大学社会科学研究科博士課程修了。新潟大学法学部教授、九州大学法学部教授を経て、福岡大学法学部教授。九州大学名誉教授。専攻は、ヨーロッパ政治思想史、とくにトクヴィルの政治思想研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
7
地方分権と中央集権について考えさせられる良書。中央集権(パリ)が現在まで変わらなかったフランス。地方分権への警戒は、民族学者達が指摘するように虐殺弾圧されてきた民族に地方分権を与えるとナショナリズムに至るから。それなら弾圧に任せる中央集権全体主義(スターリニズム、ファシズム)を静観しているほうがマシ、という見解に欧州は結果的に至る。ユーゴへの中途半端な態度はそれに起因するか。米は、仏と違いタウンミーティングが機能しているとトクヴィル。しかし行政的なTMは後付けで、TMがなければ死ぬような環境だったから。2016/05/12
Fumoh
3
同文庫で「旧体制と大革命」を翻訳した小山氏のトクヴィル論ですが、実際かなり分かりにくい本になってしまっています。まずトクヴィルの「民主主義的専制」や「自由なき平等」といった概念が、現代においても理解の難しいものであること。というのは、それは「個人」という地点においても「社会」という地点においても別個の現象であるのに、それを分けて語ることが難しいこと(お互いに強く依存し合っているような関係であること)。また政治システムの実験は行えないこと。また政治というのは実務的なものであり、習俗や民衆感情に照らし合わせて2025/02/06
Ise Tsuyoshi
2
「トクヴィルにとって最も恐るべきは、専制を可能にする『自由なき平等』である」(p.42)「個々人は古い絆から解放されても、『自立した弱い存在』でしかない…市民は独力でもはやできないことを『より熟達した活動的な政府』に委ねなければならないのか。トクヴィルはそうではないと応える」(p.327)。行政的専制への対抗策として、トクヴィルは地方自治、陪審制、アソシアシオンという「民主主義の3つの学校」を挙げる。アメリカを論じる時に念頭に置かれているのは当時のフランス社会だが、現代の日本が抱えている課題にも通じる。2020/12/03