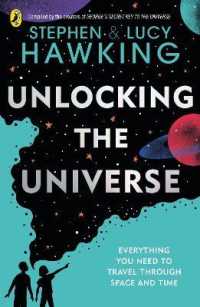出版社内容情報
警察、地方、厚生労働、国土交通、神社…、巨大すぎる「省庁の中の省庁」を通史と多様なテーマで論じ、近代日本を考える決定版!
内容説明
民主主義の敵か、近代日本の立て役者か―。人々の生活全般を所管し、他の省庁を圧倒した「省庁の中の省庁」は、いかに生まれ、いかに衰退していったのか。近代日本の政治と行政のあゆみを辿りながら、現代日本の淵源ともいうべき巨大すぎる官庁の実像を描き出す。
目次
序論 内務省―政治と行政のはざまで
通史編(「省庁の中の省庁」の誕生―明治前期;内務省優位の時代―明治後期~大正期;政党政治の盛衰と内務省―昭和戦前期;内務省の衰退とその後―戦中~戦後期)
テーマ編(近代日本を支えた義務としての「自治」―地方行政;戦前の「国家と宗教」―神社宗教行政;権力の走狗か、民衆の味方か―警察行政;感染症とどう向き合ってきたか―衛生行政;河川・道路政策の展開と特質―土木行政 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
118
官庁とは政治家の下で動く官僚組織であり、トップの力量次第で強くも弱くもなる。旧内務省も大物政治家が大臣に任ぜられ、広範な権限をフル活用したからこそ官界に君臨できた。このため他官庁を圧倒する権力を振るう一方で、内閣が交代すれば党の系列官僚が地方警察部長に送り込まれるなど政争の影響をもろに受けた。もともと大久保利通が中央集権国家を創るため様々な部門を集めて設けた組織なので、巨大化すると専門性の高い分野が独立性を強め遠心力が働いてしまったのだ。時代に必要とされた官庁がやがて見放される組織論として興味深く読んだ。2025/07/02
うえぽん
49
日本政治史研究者による研究会のメンバーが、通史編とテーマ編で内務省の全体像を分析・紹介した本。同省は近代日本の政治・行政全般の象徴と考えられるのに研究蓄積に乏しく、現代政治・地方自治研究との接点も薄い点に問題意識がある。大蔵省から分離した黎明期はまだ省庁の中の省庁と言える状況にはなく、明治後期〜大正期の同省優位の時代を経て、政党政治や各省、軍との軋轢の中で、昭和期に衰退傾向に陥る流れが理解できる。各行政分野においても戦前からの連続的な制度発展が分かる点に加え、際立つ政治家や官僚の生き様も垣間見える意欲作。2025/04/30
Tomoichi
30
研究者が共同で立ち上げた内務省研究会による内務省の歴史や各テーマに焦点を絞った論考など新書らしからぬ分量の本書は、買って損はない。私たちがイメージする内務省が如何に左翼が作り上げた幻想か理解できた。現代的でいえば巨大官庁だが、所詮官庁でしかないのである。つまり政府や国会などに振り回される姿は現在の諸官庁と変わらない。フランスには内務省が存在するからファシズム国家という話は聞いた事はない。どんな組織も運用次第で悪にも善にもなりうるっていう普通の話。左翼のつけた印象を払拭できた本書の意義は大きい。2025/07/26
BLACK無糖好き
20
中堅・若手研究者による内務省研究会のメンバーを中心に執筆された模様。内務省の成立から解体、その後の日本の政治や社会への影響までを辿った「通史編」と、内務省の持つ多様な行政を個々に扱った「テーマ編」で構成されている。地方行政の人事権を握っていたのは、影響力を行使する上でも大きかった。注目したのは、戦時期の本土決戦に備えた軍部発案の国民動員体制をめぐる内務省の抵抗。連合軍上陸による国土分断に備えた地方機関である地方総監府に対する主導権を握り、地方総監府の軍政機関化を防いだとの経緯は興味深いものがある。2025/11/08
どら猫さとっち
17
内務省。日本で一番肝心な巨大官庁。その歴史を辿った研究書。地方行政、警察行政、土木行政、衛生行政など、今の日本社会を支える官庁。歴史として興味深く読んだが、現在この機関はちゃんと機能しているのか、疑問視することも読み終えてある。大久保利通といった幕末の人物から、伊藤博文や原敬などビッグネームが名を連ねていながら、名も知らない人たちの活躍も、内務省を支えたことも忘れてはならないことである。2025/06/11