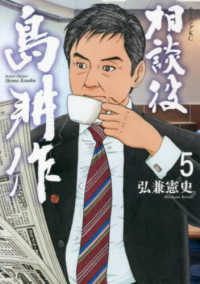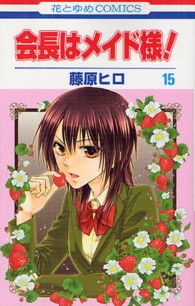出版社内容情報
人間は、どのようにしてモラルを持つようになったのだろう? 助け合うよう生まれついているはずなのに、今や普遍的なモラルなど失われたかのようだ。だが、人類が共有するモラルは存在する。モラルの起源が理解できれば、モラルの未来も見えてくる。
生物学的、文化的に社会が進化していく過程でモラルはどのように形成されたのか――哲学の専門知識とさまざまな研究データをもとに解明。現在の私たちのあり方を決定づけた進化の歴史が明らかになる。
狩猟時代から現代に至るまで、人間のモラルの基本は「個人の利益<共同体の利益」である。脆弱なホモサピエンスが生き延びるには、それは最良の手段だったからだ。5万年の歴史を通して、社会的構造の変化とその後の経済発展により、モラルはさまざまな変容を遂げてきたが、基本は今なお変わらない。
人間の善と悪はどのようにつくられてきたか? 歴史の流れを軸に、哲学、経済、生物学的な分析をもとに「モラルの変遷」を説明。
かつてない不平等と分断の時代、他者に限りなく不寛容で、モラルに反するものを厳しく罰し、個人主義が浸透しすぎた時代、どのように新たなモラルをつくるべきか?
著者の結論は人間のモラルの基本に立ち戻ること。国・民族・宗教などを問わずに人類に共通する「個人の利益<共同体の利益」を新たなモラルにすべきだというものである
内容説明
石器時代の「集団で生きるためのルール」から現代の人種・ジェンダー・マイノリティ差別、言葉狩りやキャンセルカルチャーまで言及。共生のための「今と未来の課題」を明かす。行き過ぎた正義は「悪」になるのか?気鋭の哲学者が500万年にわたって「人類の善と悪」の変遷を追う!
目次
第1章 五〇〇万年―新しい系譜学
第2章 五〇万年―罪と罰
第3章 五万年―欠陥動物
第4章 五〇〇〇年―不平等の発明
第5章 五〇〇年―奇妙さの発見
第6章 五〇年―歴史の教訓
第7章 五年―非政治的考察
著者等紹介
ザウアー,ハンノ[ザウアー,ハンノ] [Sauer,Hanno]
1983年生まれ。オランダ・ユトレヒト大学哲学・宗教学部准教授。善と悪、モラルをテーマに数々の論文を発表しており、2019年には欧州研究会議から若手研究者向けの助成金を、2020年にはオランダ王立芸術科学アカデミーより有望な若手研究者に贈られるアーリーキャリアアワードを授与されている。ドイツ・デュッセルドルフ在住
長谷川圭[ハセガワケイ]
高知大学卒業。ドイツ・イエナ大学修士課程修了(ドイツ語・英語の文法理論を専攻)。同大学講師を経て、翻訳家および日本語教師として独立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
クリママ
ta_chanko
ヨンデル
月をみるもの
-

- 電子書籍
- 砂漠の花嫁【タテヨミ】第36話 pic…
-

- 電子書籍
- 朽ちた花びら 病葉流れて II 幻冬舎…