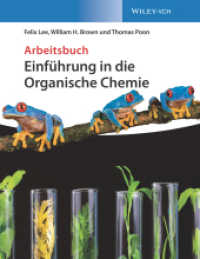出版社内容情報
唐代に、陸羽によって著された世界最古の茶書『茶経』が、中国茶書の古典として知られています。
本書は『茶経』に次ぐ重要茶書二書の全訳注版です。
明代の偉大なる茶人(茶の愛好者)によって書かれた貴重な書です。
日本の煎茶道や最近盛んになりつつある中国茶の源流ともいえるのが、明代に行われていた「喫茶」です。
明代には、茶の文化が隆盛をしており、数多の茶書が著されましたが、
それ以前の茶書の剽窃や焼き直しがほとんどでした。
そういった中にあって、本書で取り上げる『茶疏』と『茶録』は、独自の探究によって書かれた貴重な茶書です。
よい産地、製茶法、貯蔵法、水の選び方、茶葉の投げ入れ、茶器の選択、飲み方、客人の迎え方、などなどを具体的に描きます。
茶を、おいしく、楽しく、清らかに飲むやり方を追究します。
中国の茶道は、精神性を最重視する日本の茶道とは少々趣を意にして、実用的な内容が充実しているのは文化の違いなのでしょうか。
中国のみならず、日本にも伝わり、江戸時代には上田秋成『清風瑣言』をはじめ、多くの書物にも引用され、おおきな影響を与えています。
全訳注として、
【訓読】【現代語訳】【原文】【注釈】
を加えました。
喫茶愛好家必携の一冊です。
本書は、訳し下ろしです。
【目次】
まえがき
1 張源『茶録』
張源『茶録』について
凡例
茶録引 顧大典
採茶
造茶
弁茶
蔵茶
火候
湯弁
湯有老嫩
泡法
投茶
飲茶
香
色
味
点染失真
茶変不可用
品泉
井水不宜茶
貯水
茶具
茶盞
拭盞布
分茶盒
跋茶録 沈周
2 許次しょ『茶疏』
許自しょ『茶疏』について
許自しょ伝
凡例
題許然明茶疏序 桃紹憲
茶疏小引 許世奇
凡例
産茶
今古製法
採摘
炒茶
〓(山+介)中製法
収蔵
置頓
取用
包せき
日曜頓置
択水
貯水
〓水
煮水器
火候
烹点
秤量
湯候
甌注
とう滌
飲〓
論客
茶所
洗茶
童子
飲時
宜輟
不宜用
不宜近
良友
出遊
権宜
虎林水
宜節
辯訛
攷本
内容説明
煎茶道や中国茶道の源流、ここにあり。茶文化隆盛の明代の二書『茶録』『茶疏』は、時代を超えた実践的な知恵の宝庫である。産地、製茶、貯蔵、水から淹れ方、茶寮、茶器、飲み方、さらには客人の迎え方、心持ちまでを具体的に教える。“訓読”“現代語訳”“原文”“注釈”で構成。理解を助ける図版も収録。清く、楽しく、美味しく味わう指南書の古典。
目次
張源『茶録(張伯淵茶録)』(張源『茶録』について;張源『茶録(張伯淵茶録)』)
許次〓『茶疏』(許次〓『茶疏』について;許然明茶疏)
著者等紹介
張源[チョウゲン]
字は伯淵、号は樵海山人。洞庭山に隠棲した文人と思われる
許次〓[キョジショ]
1549‐1604年。中国の茶人、文人。嗜茶賞石(茶をたしなみ、石を愛でて収集する)の趣味があり、詩文をよくしたとされる。老荘思想を好んだ
岩間眞知子[イワママチコ]
東京生まれ。早稲田大学文学研究科(美術史)修士課程修了。東京国立博物館特別研究員などを経て、人間文化研究機構研究員、日本医史学会代議員。現在、静岡県ふじのくに茶の都ミュージアム客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふら〜
tokumei17794691
-

- 洋書
- Seducción