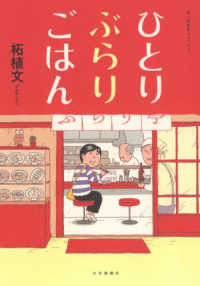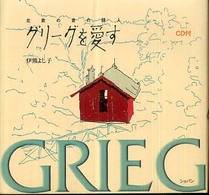出版社内容情報
教育勅語・御真影から「日の丸・君が代」、元号法まで。明治維新から令和に至る、日本の近代教育と天皇制の関係性を考察する。
「御真影」を救うため火中に飛びこみ「殉職」した校長――単なる「紙切れ」は、いかにして「神聖」とされるに至ったのか? 「教育勅語」と「御真影」が当初の目的を逸脱し、「絶対視」されてゆく戦前の過程を丹念にたどる。また、敗戦によりいったん無効と公的に宣言された「教育勅語」が、にもかかわらず、既成事実の積み重ねにより復権を果たしてゆく戦後の過程も客観的に叙述する。教育への国家介入の危険性に警鐘を鳴らす力作。
内容説明
国民にとって教育とは何か。明治維新から令和まで、日本の近代教育と天皇制の関係性を考察する。
目次
第1章 明治初期の天皇制と教育
第2章 教育勅語の発布と御真影・学校儀式
第3章 日露戦争前後の教育勅語・学校儀式
第4章 国民精神作興と御真影・学校儀式
第5章 ファシズム的状況における教育勅語・学校儀式
第6章 戦後教育と象徴天皇制
第7章 1970年代以降の天皇・天皇制と教育
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
60
著者は同世代の教育史研究者で、明治以降の天皇制すなわち「国体」を、教育を通じでどう国民に浸透・定着させようとしたかという点について、御真影と教育勅語という具体的な「道具」の扱われ方の変遷を通して描いている。またアジア太平洋戦争後の占領政策の中でのこれらの扱いについても詳述、特に田中耕太郎の果たした役割が大きく、中公新書の評伝に興味を持った。一方で「日の丸」「君が代」問題にも踏み込んでいて、著者の問題意識の方向性をよく表している。自分自身がこの問題の一方の当事者であり、この整理に関してはほぼ同意できた。2023/09/19
樋口佳之
51
教育勅語、まして恣意的現代訳や、徳目の列挙だけを議論してはだめだなあって感想を持ちました。タイトル通り、教育勅語と御真影、近代天皇制と教育を全体としてみないと。/一方、戦前の帝国主義国としての成長と大破綻、戦後の経済大国としての成長と転落過程にある現在、一応民主主義の価値観を共有するってお話や、新自由主義の跋扈の中で、命よりも御真影が大事とされた時代のイデオロギーの再現は無理なのでは。/名ばかり「国葬」を執り行う事を恥じない保守政治家とジェンダー平等を訴える若き女性皇族。衰えてゆく国の不可思議な対立点。2024/02/20
carrion_crow
6
研究者の人が一般の人向けに書いた堅めの解説書という感じの本で、原文/現代語訳並記だが原文は読み飛ばしながら読んだ。戦前の各時代においても、教育勅語の扱いが変わって行った変遷が詳しく解説されている。 特に印象的だったのは社会情勢に応じて教育勅語と並ぶような勅令がしばしば出されたという話で、なるほど3.11後の天皇ビデオメッセージというのはこの文脈に並ぶものなのかもしれないな……などと思った。 なお言うまでもなく、天皇制は廃止するべきである。2023/08/25
chietaro
6
時間かかったけど、読み終えました。政府から見た課題を通知で押さえ込んでいくのは、今とかわらないと思いながら読みました。戦前戦後の教育の流れがわかり、勉強になりました。2023/07/14
我門隆星
3
いわゆる「教育勅語」が出てから、終戦までと思いきや、戦後教育まで話は続く。いや、確かに、「教育勅語復活」の動きは政界の中にもあるといえばあるのだが。そこはどうだろう。「敗戦」を「終戦」と糊塗して戦後政界をゾンビのごとく牛耳った戦時中の政界をもう少し切り込まなければ、戦後教育の話はキツイ。また、それをやると、「政界の一貫性」になって「御真影どこにいった」となりかねない。となれば、戦後の話はもっと簡単に書いたほうが良くはないか。
-

- 電子書籍
- あまりにも悲劇な世界史 - アンビリー…