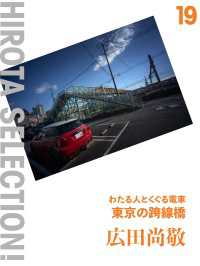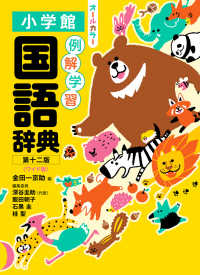出版社内容情報
ADHDやASDを病いと呼ぶのなら、「普通」も同じように病いだーー
「色、金、名誉」にこだわり、周囲の承認に疲れてしまった人たち。
「いいね」によって、一つの「私」に束ねられる現代、極端な「普通」がもたらす「しんどさ」から抜け出すためのヒント
●「自分がどうしたいか」よりも「他人がどう見ているか気になって仕方がない」
●「いじわるコミュニケーション」という承認欲求
●流行へのとらわれ
●対人希求性が過多になる「しんどさ」
●本音と建て前のやり取り
●社会のスタンダードから外れていないか不安
●ドーパミン移行過剰症としての健常発達
●親の「いいね」という魔法
「病」が、ある特性について、自分ないしは身近な他人が苦しむことを前提とした場合、ADHDやASDが病い的になることがあるのは間違いないでしょう。一方で、定型発達の特性を持つ人も負けず劣らず病い的になることがあるのではないか、この本で取り扱いたいのは、こういう疑問です。たとえば定型発達の特性が過剰な人が、「相手が自分をどうみているのかが気になって仕方がない」「自分は普通ではなくなったのではないか」という不安から矢も楯もたまらなくなってしまう場合、そうした定型発達の人の特性も病といってもいいのではないか、ということです。――「はじめに」より
内容説明
「色、金、名誉」にこだわり、周囲の承認に疲れてしまった人たち。「いいね」によって、一つの「私」に束ねられる現代、極端な「普通」がもたらす「しんどさ」から抜け出すためのヒント。
目次
第1章 いじわると健常発達者(診察室にやってくるAちゃん;「空色ランドセルがかぶった事件」 ほか)
第2章 ニューロティピカル症候群の生き難さ(「健常発達症候群」;挑発的なパロディー;ADHDの脳科学―遂行機能と報酬系 ほか)
第3章 ほんとうは怖い「いいね」と私(アイデンティティが奪い返されるかもしれない不安;良いおっぱい・悪いおっぱい ほか)
第4章 昭和的「私」から「いいね」の「私」へ(仲間内で「いいね」を獲得する;ハンス少年の馬恐怖;去勢されないのではないかという恐怖 ほか)
第5章 定住民的健常発達者とノマド的ADHD(向こう側を持たない世界の「いいね」;「いいね」に疲れてしまった人の突破口 ほか)
著者等紹介
兼本浩祐[カネモトコウスケ]
1957年生まれ。京都大学医学部卒業。現在、愛知医科大学医学部精神科学講座教授。専門は精神病理学、神経心理学、臨床てんかん学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
breguet4194q
アキ
ゆいまある
niisun
shikashika555