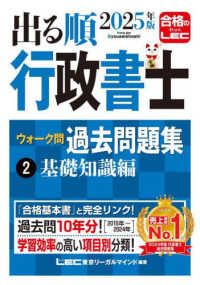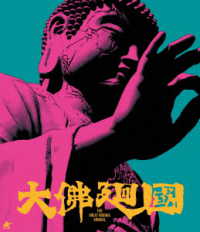出版社内容情報
「打楽器を持たない民族はいない」。古来、人は自身の体やモノを叩いて感情を伝え、動物の鳴き声や雨風などの自然音を真似、再現してきました。楽器発祥から2万年。信仰の祭礼、政治儀式、軍事の士気高揚・・・・・・あらゆる場面に浸透していった「音」と「音楽」。気候風土や時代背景に合わせ、世界各地の「音」は、どのように姿を変えてきたのか。西洋音楽と民族音楽、その対比が示す真意は? 「音」で考える、ユニークかつ雄大な文化人類学!(解説・森重行敏)
本書の原本は『世界楽器入門 好きな音 嫌いな音』(1989年1月 朝日選書)を改題したものです。
はじめに
第一章 ミンゾク楽器・
第二章 楽器の起源
1 生活周辺から生まれた楽器
2 食器から楽器へ
3 道具から楽器へ
4 自然界の音の再現から楽器へ
5 生存に必要な音を出す道具から楽器へ
6 呪術・信仰の道具から楽器へ
7 学問・研究の道具から楽器へ
8 音像から楽器へ
第三章 楽器分類を通して見た諸民族の楽器観
1 中国
2 インド
3 ギリシャ
4 ローマ
5 ヨーロッパ
第四章 楽器の音
1 打つ、擦る、吹く、弾く
2 楽器の成り立ち
3 音の出し方
第五章 楽器の分布と歴史
第六章 風土と音
1 風土と楽器
2 音の響き
第七章 音・数・楽器
第八章 メディアとしての楽器
1 経営メディアとしての楽器
2 視覚メディアとしての楽器
3 思想メディアとしての楽器
第九章 手作りについて
第十章 好きな音嫌いな音
第十一章 東方の楽器・西方の楽器
石笛/横笛/笙/篳篥/尺八/和琴/箏/琵琶/三味線/胡弓/鼓
/先史時代の楽器/オーボエとバスーン/クラリネット/トラムペ
ットとトロムボーン/ホルン/テューバ/リコーダーとフリュート
/バグパイプ/オルガン/キタラとライア/ハープ/ヴァイオリン
/リュートとギター/ツィターとハープシコード/クラヴィコード
とラングライク/ダルシマーとピアノ/カリヨン/ティンパニとシ
ムバル/アフリカの楽器/インドの楽器/インドシナ半島の楽器/
インドネシア・オセアニアの楽器/雑音の効果/種々の撥/弦
楽器に関する参考文献
あとがきにかえてーー楽器研究の方法論――
解説「人類共通の財産ーー音楽とは何か?ーー」森重行敏(洗足学園音楽大学現代邦楽研究所所長)
楽器索引
人名索引
内容説明
「打楽器を持たない民族はいない」。人は古来、動物の鳴き声や自然音を模倣し、手や体、モノを叩いて感情を伝えてきた。「楽器」発祥から約二万年。宗教や政治、軍事儀式へと用途を拡げ、各地の風土や時代に合わせて、変遷を遂げた世界中の楽器たち。人類が模索、創造し続けた無二の「音」の醍醐味を、文化人類学的視点で堪能する!
目次
ミンゾク楽器
楽器の起源
楽器分類を通して見た諸民族の楽器観
楽器の音
楽器の分布と歴史
風土と音
音・数・楽器
メディアとしての楽器
手作りについて
好きな音嫌いな音
東方の楽器・西方の楽器
著者等紹介
郡司すみ[グンジスミ]
1930年フィンランド・ヘルシンキ生まれ。国立音楽大学名誉教授。国立音楽大学楽器学資料館初代館長。楽器学専攻。西ドイツ・ルードヴィクスブルクFachschule fur Musikinstrumentenbau(楽器製作専門学校)卒業。2019年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コットン
へくとぱすかる
YO)))
やま
ひでお