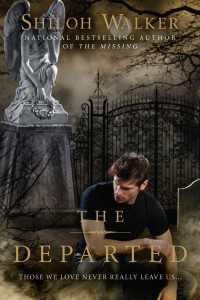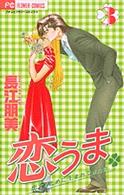出版社内容情報
浜中 淳[ハマナカ ジュン]
著・文・その他
内容説明
ニトリ、ツルハ、DCM北の大地から続々トップ企業が誕生!「小売り不毛の地」と言われた北海道から全国制覇を目指した、熱き経営者たちの挑戦。
目次
プロローグ 北海道から全国へ
第1章 1998年の“北海道現象”
第2章 “危機”を乗り越えて―ツルハとニトリの並走
第3章 “流通革命”の旗手
第4章 究極の“3極寡占市場”
第5章 セブン‐イレブンも勝てなかったコンビニ
第6章 ハブ・アンド・スポーク―北海道企業の未来
著者等紹介
浜中淳[ハマナカジュン]
北海道新聞社経済部デジタル委員。1963年東京生まれ。北海道大学経済学部経済学科卒、1989年北海道新聞社入社。記者として浦河支局、旭川支社報道部、東京支社政治経済部、札幌本社経済部などに勤務。2016年論説委員、2020年札幌本社経済部長を経て、2022年7月から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。