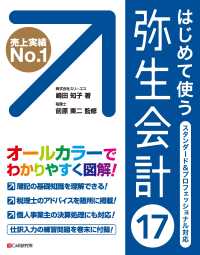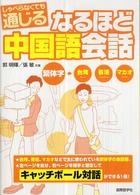出版社内容情報
江利川 春雄[エリカワ ハルオ]
著・文・その他
内容説明
明治以来、日本人は英語の習得にずっと悩み続けてきた。小学校の英語授業は是か非か、必要なのは文法訳読か会話か、全員必修は必要か、そもそも外国語は「英語だけ」でいいのか―。「英語科廃止論」の急先鋒・藤村作、「カムカム英語」の平川唯一、加藤周一の義務化反対論、平泉渉「改革試案」の衝撃、筑紫哲也、松本道弘と中村敬の「英語帝国主義論争」。文明開化から、大正期の教養主義、「敵国語」だった戦時下を経て、グローバル化の現代まで、時代の論客たちがぶつかり合う。
目次
第1章 早く始めれば良いのか?―小学校英語教育論争(明治期)
第2章 優先すべきは訳読か?会話か?―文法訳読vs.話せる英語論争(明治‐大正期)
第3章 目的は教養か?実用か?―中等学校の英語存廃論争(大正‐昭和戦前期)
第4章 英語は全員に必要なのか?―「カムカム英語」と英語義務化論争(昭和戦後初期)
第5章 国際化時代に必要な英語とは?―平泉‐渡部「英語教育大論争」(昭和後期)
第6章 外国語は「英語だけ」でよいのか?―英語帝国主義論争(平成期)
終章 そもそも、なぜ英語を学ぶのか?―英語教育論争史が問いかけるもの
著者等紹介
江利川春雄[エリカワハルオ]
1956年、埼玉県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業、神戸大学大学院教育学研究科修士課程修了。広島大学で博士(教育学)取得。専攻は英語教育学、英語教育史。和歌山大学名誉教授。日本英語教育史学会名誉会長。著書に『近代日本の英語科教育史』(東信堂、日本英学史学会豊田實賞受賞)、『日本の外国語教育政策史』(ひつじ書房、日本英語教育史学会著作賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
Nobu A
Riopapa
yo_c1973111
siomin