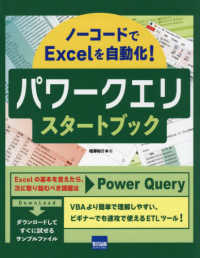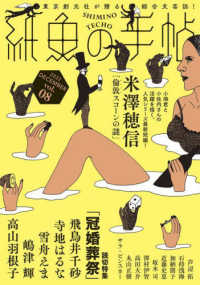出版社内容情報
遠藤 利彦[エンドウ トシヒコ]
監修
内容説明
子どもの発達を支え、感情を整える。「不安なときに守ってもらえる」という確信が心の力に。アタッチメントの形成から生涯にわたる影響まで解説!
目次
よくあるとらえ方 「アタッチメント(愛着)」ってなんのこと?
第1章 子どもの発達とアタッチメント
第2章 アタッチメントの個人差と問題
第3章 心の力を育む「基地」の役割
第4章 保育・教育の場でのかかわり方
第5章 大人にとってのアタッチメント
著者等紹介
遠藤利彦[エンドウトシヒコ]
1962年生まれ。東京大学教育学部卒。同大学院教育学研究科博士課程単位取得後退学。博士(心理学)。聖心女子大学文学部講師、九州大学大学院人間環境学研究院助教授、京都大学大学院教育学研究科准教授などを経て、東京大学大学院教育学研究科教授。同附属発達保育実践政策学センター(Cedep)センター長。日本学術会議会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よむよむ
24
ある種の愛着障害と思われる子の対応に日々悩み続ける中、少しでもヒントがあればと本書を読む。アタッチメントの重要性はイヤというほど知っているつもりだが、園で細心の注意を払い配慮に配慮を重ねても、家庭で全く別のベクトルが働いているならその努力はなに?と虚しくなるときがある。2023/08/20
ひろか
9
ほんと、このシリーズはハズレがない。薄い冊子であるが、必要な情報が網羅。こういう本は、「監修」としかないので、編集部である程度作っておいて、第一人者の先生に監修してもらうという作り方なのでしょうか。ま、いずれにしてもすごい。2022/09/04
めぐ
8
養育者と子どもの愛着形成の具体的なやり方とその影響を分かりやすく図解した本。泣く子には一度共感してみせてから慰める、立て直しからの映し出しを両立させるともっとも早く泣き止み落ち着く。感情の名前を言葉にして与えていく、などが参考になった。心掛けていきたい。2023/08/02
Flac
4
このシリーズはとっかかりにすごくいい。2023/04/17
がりがり君
3
新書なんかで断片的に知ってたアタッチメントという概念ですが、本書でようやく体系的に勉強できたかなと。心理学の最前線では精神分析学じゃなくてアタッチメントが盛んに研究されてるし、MBTIじゃなくてビッグファイブが手法として取り入れられてるんですよね。ビッグファイブなんかじゃ差がなかったASD児とTD児の間でアタッチメント形成に差があるらしい。愛着障害児と発達障害児はよく似てるという話もありますし色々情報を総合すると発達障害児の問題はアタッチメントなんじゃないか。しらんけど。2023/10/04
-

- 電子書籍
- 5分後に涙 スターツ出版文庫
-
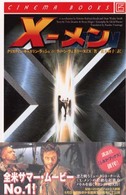
- 和書
- X-メン シネマブックス