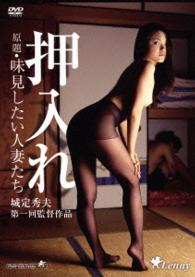出版社内容情報
12世紀末に臨済宗開祖・栄西が中国から持ち帰って以降、
日本人に欠かせない飲み物となった日本茶。
その味と製法はどのように変わり、私たちに受け継がれたのか?
茶畑の日光状態とうまみの関係、番茶・煎茶が誕生した理由、
幕末の海外輸出秘話から、多彩な茶葉の特徴と製法、淹れ方や茶器選びまで――。
長く深く愛された、日本の「心」を味わい尽くす!
*本書は2006年に刊行された『お茶は世界をかけめぐる』(筑摩書房)を改題したものです。
内容
プロローグ 日本茶セミナー
第一章 村上の春
第二章 煎茶以前のこと
第三章 煎茶の発明
第四章 世界に旅立つ日本茶
第五章 世界をめぐる日本茶
第六章 日本茶故郷へ帰る ーー台湾から見た日本茶の高度成長
第七章 日本茶の現在
エピローグ 釡炒り茶の復権
内容紹介)
三代将軍家光の時代には、宇治から江戸まで碾茶の新茶を運ぶ、お茶壺道中が定例化されます。(中略)あの、「♪ズイズイズッコロバシ……」という戯れ唄にある「♪茶壺に追われてトッピンシャン、抜けたらドンドコショ……」という一節は、十万石の大名行列と同等の格式をもって旧暦六月前後の農繁期に行われたお茶壺道中に対する、沿道からの怨えん嗟さ の反応でした。「またあの面倒なお茶壺が来るなあ」―――第二章「煎茶以前のこと」より
あとがき
コラム〈日本茶データファイル〉
1 碾茶
2 煎茶
3 玉露
4 釡炒り茶
5 蒸し製玉緑茶
6 お茶の葉の選び方
内容説明
一二世紀末に臨済宗開祖・栄西が中国から持ち帰って以降、日本人に欠かせない飲み物となった日本茶。その味と製法はどのように変わり、私たちに受け継がれたのか?茶畑の日光状態とうまみの関係、番茶・煎茶が誕生した理由、幕末の海外輸出秘話から、多彩な茶葉の特徴と製法、淹れ方や茶器選びまで。長く深く愛された、日本の「心」を味わい尽くす!
目次
プロローグ 日本茶セミナー
第1章 村上の春
第2章 煎茶以前のこと
第3章 煎茶の発明
第4章 世界に旅立つ日本茶
第5章 世界をめぐる日本茶
第6章 日本茶故郷へ帰る―台湾から見た日本茶の高度成長
第7章 日本茶の現在
エピローグ 釜炒り茶の復権
著者等紹介
高宇政光[タカウマサミツ]
1949年、東京都生まれ。茶商。思月園代表取締役。日本茶インストラクター第一期生、日本紅茶協会のティーインストラクター資格保有。1994年より日本茶セミナーを開始。1999年、フロリダでの全米茶業者大会を皮切りに、ドイツ、ベルギー、台湾など、海外での日本茶セミナーも精力的に行う。2021年7月逝去。同年、創業90年の思月園も閉店(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムカルナス
さく
あひる
鴨の入れ首