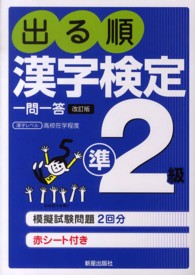出版社内容情報
本書の著者ピエール・アド(1922-2010年)は、古代ギリシア思想や新プラトン主義の研究者として、コレージュ・ド・フランス教授を務めました。その著作は、古代哲学のみならず、フランシス・ベーコンやデカルトなどの17世紀思想、ゲーテ、ヘーゲルからニーチェ、ベルクソン、ハイデガーに至る19~20世紀の思想まで、幅広い知識に裏打ちされた類を見ない豊饒さをそなえています。その著作はヨーロッパの知識人に大きな影響を与えるとともに、アメリカでも多くの読者を獲得してきました。
ところが、日本では2020年に『イシスのヴェール』(法政大学出版局)が出版されるまで、訳書は1冊も存在せず、それゆえ注目を浴びることもなかったというのは、豊かな翻訳文化を育ててきた国では奇妙な欠落だったと言わざるをえません。2021年には『生き方としての哲学』(法政大学出版局)の邦訳が出版され、ようやく日本でもこの碩学の思想に触れる準備が整いつつあります。今こそ、アドがフランスで初めて本格的にウィトゲンシュタインを紹介した人物でもあること、そして唯一無二の解釈を残していたことを伝える本書を読むべき時だと言うことができるでしょう。
研究者にさえ顧みられずにきた本書に収められた論考は、『論理哲学論考』と『哲学探究』しか出版されていなかった時期に書かれたものにもかかわらず、後続の者が見出すことのできなかった側面を明確に浮かび上がらせるものにほかなりません。アドは深い教養に導かれて、ウィトゲンシュタインの思想の中に古代のストア派や懐疑主義、新プラトン主義とのつながりを、あるいはショーペンハウアーとのつながりを見て取ります。その結果、ウィトゲンシュタインの著作は独自の「哲学」を記述しただけのものでなく、第一級の「哲学史」でもあることを明らかにするのです。
本訳書では、アドの解釈の画期性をよりよく理解できるよう、気鋭のウィトゲンシュタイン研究者である古田徹也氏の重厚な「解説」を収録しました。さらに「訳者後記」では、合田正人氏がアドという人物を中心にした知的ネットワークの広大さを深い思い入れとともに綴っています。本書の中で、これまで知らなかったウィトゲンシュタインの顔を見ることができるでしょう。
今後のウィトゲンシュタイン研究にも大きな一石を投じることになる重要著作の邦訳を選書メチエの1冊としてお届けいたします。
[本書の内容]
序
ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』における言語の限界についての考察
ウィトゲンシュタイン 言語の哲学者 I
ウィトゲンシュタイン 言語の哲学者 II
言語ゲームと哲学
解説 ウィトゲンシュタイン哲学の「新しい」相貌(古田徹也)
訳者後記
内容説明
本書の著者ピエール・アド(一九二二‐二〇一〇年)は、新プラトン主義をはじめとする古代ギリシア思想の専門家として権威あるコレージュ・ド・フランスの教授を務めた碩学である。近年邦訳が刊行され始め、日本でもその名を知られつつあるアドがフランスに初めてウィトゲンシュタインを導入した人物であることはしかしほとんど知られていない。『論理哲学論考』と『哲学探究』以外の全容が知られていなかった時期に執筆された本書をなす論考には、後代の研究者にも気づかれなかった哲学者の秘められた横顔が確かに浮かび上がっている。真に「哲学」を記述することは「哲学史」そのものとなる。
目次
ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』における言語の限界についての考察
ウィトゲンシュタイン 言語の哲学者1
ウィトゲンシュタイン 言語の哲学者2
言語ゲームと哲学
著者等紹介
アド,ピエール[アド,ピエール] [Hadot,Pierre]
1922‐2010年。パリで神学教育を受け、司祭の資格を得たあと、ソルボンヌで神学・哲学・文献学を学ぶ。二七歳でフランス国立科学研究センター(CNRS)の研究員となり、哲学の道に進む。文献学に基づいた古代ギリシア思想や新プラトン主義の研究を専門とした。フランスで初めてウィトゲンシュタインについて論じたことでも知られる
合田正人[ゴウダマサト]
1957年生まれ。現在、明治大学文学部教授。専門は、フランス思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
⇄
Go Extreme
いかくん
um
-

- 電子書籍
- &フラワー 2025年7号 &フラワー
-
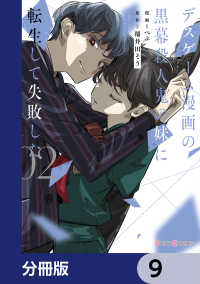
- 電子書籍
- デスゲーム漫画の黒幕殺人鬼の妹に転生し…