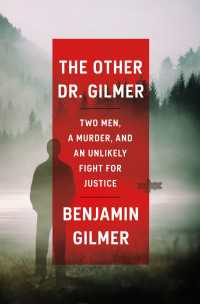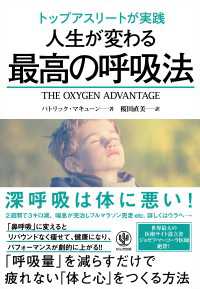出版社内容情報
小熊 英二[オグマ エイジ]
著・文・その他
内容説明
書く方法がわかれば、勉強はもっと面白くなる。大学での双方向授業をもとにした“論文入門”の決定版!
目次
論文とは何か
科学と論文
主題と対象
はじめての調べ方
方法論(調査設計)
先行研究と学問体系(ディシプリン)
方法(メソッド)
研究計画書とプレゼンテーション
構成と文章
注記と要約〔ほか〕
著者等紹介
小熊英二[オグマエイジ]
東京都生まれ。東京大学農学部卒。出版社勤務を経て、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。現在、慶應義塾大学総合政策学部教授。学術博士。主な著書に『単一民族神話の起源』(サントリー学芸賞)、『“民主”と“愛国”』(大佛次郎論壇賞、毎日出版文化賞、日本社会学会奨励賞)、『1968』(角川財団学芸賞)、『社会を変えるには』(新書大賞)、『生きて帰ってきた男』(小林秀雄賞)、A Genealogy of“Japanese”Self‐Imagesなど(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gonta19
104
2023/11/18 ジュンク堂三宮駅前店にて購入。 2025/2/7〜2/14 論文をどのように書けば良いか、を詳細に解説した内容。論文に限らず、説得力のある文章を書く際にとても参考になる。文章が苦手な人にはぜひ読んで欲しい本だが、そういう人に限って、「本を読まない」という何とももどかしい状況もある。何とかならんかなぁ。2025/02/14
まこみや
62
『論文の書き方』『知的生産の技術』…考え方や書き方を説く新書は枚挙に暇がない。それぞれ参考にはなったが、今だに活用している本は、『理科系の作文技術』と『日本語の作文技術』の二冊である。本書は上記二冊と並んでこの先長く活用する一冊になるような気がする。就中これから論文をものしようとする学生にとっては、論文とは何か、その初歩から丁寧に指導した優れた本だと思う。ただ一つ課題がある。チャットGTPが問題となっている現在、自ら思考し作文するという非効率的な辛い作業に投企する人間がはたしてどれだけいるか、という点だ。2023/04/08
とくけんちょ
51
再読。論文の書き方とあるが、論理的な思考をするための手順本として読む。論文の形式的な部分は流し読みになるが、思考手順として学ぶところは多い。自分自身が論理的思考ができているか、つまり相手を説得できるかどうかを検証するために、論文的なものを書くという作業は効果的。そう思うようになって、書類を書くことが手間に感じなくなった。2023/05/09
さぜん
49
「論文を書くことは『人間の不完全さに気づくこと』」と著者は言う。書く前から自分の不完全さに打ちのめされているけれど。本書はテクニックではなく自分の考えを根拠と論理をもって説明することの重要さを論じている。大学で学ぶ意味ってここに集約されるのでは。2回目の修了論文に取り組んでいるが主題と対象を混同しているし、先行研究の調査もおぼつかない。ふうー、まだまだもがきそう。迷走したときに読み返したい。手元におきたい1冊。2022/07/04
ころこ
44
タイトルと内容に惹かれてという読者と、著者の本だからという読者が想定できます。前者に興味がなく、後者のタイプの読者は私が流し読みしておきましたが、その結論は読む必要が無い、というものでした。本書では形式に重心が置かれていますが、この目的のためには他の優れた本や論文の書き方をパクれば済みます。その優れた文章がなぜ書かれたのか、形式と内容が不可分であることを知ることのためにも(著者の本は決まって多くの分量を書いている)、あえて本書を読む必要は無いかと思います。2022/06/14