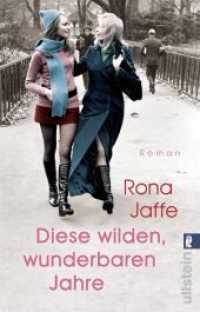内容説明
オープンダイアローグ発祥の国フィンランドでは、対話によって、精神面に困難を抱えた人の8割が回復。学校や職場、家庭、議会でも「対話の場」が開かれ、大きな効果を上げている。日本人医師として初めて、オープンダイアローグの国際トレーナー資格を得た一人である著者が、自らの壮絶な過去とオープンダイアローグに出会った必然、そして、フィンランドで受けたトレーニングの様子をつぶさに記した、オープンダイアローグをハートで感じる書!
目次
序章 対話を開く
第1章 オープンダイアローグに出会うまでのこと
第2章 発祥の地ケロプダス病院で
第3章 対話が、なぜこころを癒やすのか
第4章 オープンダイアローグによる対話風景
第5章 オープンダイアローグFAQ
著者等紹介
森川すいめい[モリカワスイメイ]
1973年、東京都生まれ。精神科医、鍼灸師。二つのクリニックで訪問診療等を行う。2003年にホームレス状態にある人を支援するNPO法人「TENOHASI(てのはし)」を立ち上げ、現在も理事として活動中。2010年、認定NPO法人「世界の医療団」ハウジングファースト東京プロジェクト代表医師、2013年、同法人理事に就任。オープンダイアローグ国際トレーナー養成コース二期生で、2020年に日本の医師としては初めてオープンダイアローグのトレーナー資格を取得した二名のうちの一人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
95
フェアな状態で対話することは、日本人が最も苦手とすることかもしれない。医師に診察を受ける患者は対等な関係を得られない。対話とはフラットな状態でありのままの心をさらすこと。椅子の位置を輪のようにすることで対話への道筋が得られる。オープンダイアローグとはフィンランドの精神科ケロプダス病院で始められ、精神病患者の8割以上で症状が回復し、薬が不要となることもある。著者は日本で初めて国際トレーナー資格を取得したが、彼自身の家族との過去に向き合うことで対話の本質を知った。最終的な目標は医療以外で対話する場を作ること。2021/08/27
けんとまん1007
84
ダイアローグ。対話。会話でなく対話。ここにポイントの一つがある。それと、装丁のこの絵。円になっていることも、ポイントの一つ。違う視点での対話。基本は、結論を出そうとするのではなく、声にだすことだと思う。人は、声をだすことで、自分の声を聴きながら、自分自身の整理にもなるのではないか。そこへ、ゆっくりと進んでいくこと。これは、治療だけなく、いろいろな場面で有効だと思う。2022/01/12
おたま
59
星野智幸の小説『だまされ屋さん』⇒『オープンダイアローグとは何か』(斎藤環)⇒『感じるオープンダイアローグ』と読んできた。先の斎藤環の本が、オープンダイアローグの思想的な背景・側面については詳しいが、その分初心者には難しい。そこで出会ったのが本書。森川すいめい自身の、フィンランドにあるケロプダス病院での体験や、トレーナーのためのトレーニングとして体験的に学んだことなどがまとめられており、オープンダイアローグについてより具体的に知ることができる。ここから『だまされ屋さん』に行くのもよいと思う。2023/01/07
ネギっ子gen
59
ただ対話するだけで、どうしてこころが癒やされるのか? オープンダイアローグ発祥の国・フィンランドでは、“対話”によって精神面に困難を抱えた人の8割が回復。日本人医師として初めて、オープンダイアローグの国際トレーナー資格を得た著者が、自らの過酷な過去とオープンダイアローグに出会った必然、そしてフィンランドで受けたトレーニングの様子を記す。「その人のいないところで、その人の話をしない」「1対1ではなく、3人以上で輪になって話す」など。著者は、鍼灸院を開業した後、精神科医に。ホームレス支援などでも注目される。⇒2021/05/13
ちゅんさん
49
『まんが やってみたくなるオープンダイアローグ』がよかったので読んでみた。まんがでどういうものか視覚的に分かっていたので読みやすかった。このオープンダイアローグ、日常で実践するのは難しいかもしれないが、“話を聞く”、“本人がいない所でその人の話をしない”、“アドバイスしない”などのエッセンスはすぐにでも取り入れられるはず。やはり人は自分の話を聞いてほしいものだ。だからしっかり話を聞きアドバイスなどせず、真摯に向き合い丁寧に反応を返すことで人は自分が尊重されていると感じ自然といい方向に向かっていく。2022/08/17
-
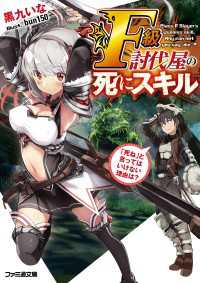
- 電子書籍
- F級討伐屋の死にスキル 「死ね」と言っ…