内容説明
教育はこれからどこへ向かうのか?子どもたちの学びのあり方はどう変わり、それを支える教育の担い手たちはどうあるべきなのか?学校施設の新しいあり方や、教育行政のあるべき姿?…新時代の教育のあり方を全方位的に指し示す、全教育関係者必読の羅針盤!
目次
第1章 自分の物語を生きるための学び―「一斉・一律」から“多様性と一貫性”へ(私の学びと公の教育;一斉・一律を乗り超える;多様性と一貫性による実践事例)
第2章 生かし合う人材と組織―「依存と孤立」から“協働”へ(学びを支え教育を担う人材;依存と孤立を乗り超える;協働による実践事例)
第3章 求めに応える施設・設備―「定型・無味」から“応答性”へ(学びと教育の場となる施設;定型・無味を乗り超える;応答性による実践事例)
第4章 引き受け支え合う行財政―「無責任」から“支援と共治”へ(教育がよりよく公で在るための行財政;無責任を乗り超える;支援と共治による実践事例)
第5章 自分たちの物語を紡ぐための公教育―「外在」から“内在”へ(よりよい公教育の追究を支える学力調査;外在を乗り超える;自分の学びと自分たちの公教育)
著者等紹介
山口裕也[ヤマグチユウヤ]
1979年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科心理学専攻修士課程修了。博士課程在学中の2005(平成17)年から研究員として杉並区教育委員会事務局杉並区立済美教育センターに在籍。同センター調査研究室長や東京学芸大学非常勤講師などを経て、杉並区教育委員会教育長付主任研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あべし
totuboy
ほうむず
pppともろー
今Chan
-
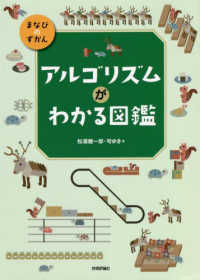
- 和書
- アルゴリズムがわかる図鑑




![パンダちゃんのきらぴかいないいないばあ [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47747/4774738891.jpg)
![七田式・知力ドリル4・5・6さいみちのり [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48614/4861486904.jpg)


