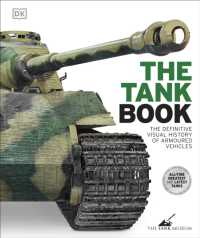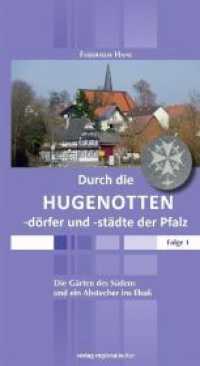内容説明
短命に終わった隋王朝の後をうけた唐王朝は、唐詩の李白・杜甫、書の顔真卿らを輩出し、文化面でも世界最高の文明を誇ったが、八世紀半ばの安史の乱を境に衰退し、九〇七年、朱全忠により滅ぼされる。中国史上唯一の女帝・則天武后、日本人僧、円仁の見た光景、ウイグル・チベットなど周辺諸国の動向もまじえ、世界帝国に生きた人々を鮮やかに描く。
目次
第1章 新たな統一国家―隋王朝
第2章 唐の再統一とその政治
第3章 安史の乱後の唐代後半の時代様相
第4章 律令制下の人々の暮らし
第5章 則天武后と唐の女たち
第6章 都市の発展とシルクロード
第7章 隋唐国家の軍事と兵制
第8章 円仁の入唐求法の旅―唐後半期の社会瞥見
第9章 東アジアの国々の動向
第10章 隋唐文化の諸相
終章 唐宋の変革の理解にむけて
著者等紹介
氣賀澤保規[ケガサワヤスノリ]
1943年長野県生まれ。京都大学文学部卒。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。佛教大学助教授、富山大学教授、明治大学教授をへて、現在、東アジア歴史文化研究所代表、東洋文庫研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
115
唐は華やか。面白い。 世界帝国、隋唐(内藤湖南の区分)。 日本の円仁は大変な時期に遭遇し、貴重な見聞録を残してくれた。”入唐求法巡礼行記” 私のやってる中国拳法の流派は終南門ていうんだけど、終南山は2604m、長安の東南郊外。詩人王維は麓の輞(もう)川荘に暮らす。2024/08/10
Tomoichi
18
恐らく歴史に興味のない人も学校で習う遣隋使・遣唐使でその名を知る隋・唐の時代のお話です。隋の時代が2代と短いからではなく、唐と連続した王朝であるのがよくわかりました。融通無碍というかある意味中華的ではない北方系的な気風がこの2王朝の面白いところであり、則天武后を産んだ土壌となった。続く五代十国を経て北宋により再統一されるが、支那文明のダイナミックさは唐で終息する気がする。2022/05/07
coolflat
16
88頁。則天武后の時代、中でもその後半期は政治は全体に内向きに傾いた。権力固めのためにエネルギーの大半が割かれたからで、いかに政治の中心に居続けることが大変であったか想像できる。その結果、長く陰山山脈一帯に押さえこまれていた突厥がまず682年唐の軛を脱して自立し、第二汗国をつくった。それに刺激されるように696年営州付近にいた契丹族が反乱を起こし、それに乗じて高句麗・靺鞨族の遺民が逃げ出し、渤海国につながる下地を築いた。体制の末端ではそれを支える府兵制や均田制や租庸調制が動揺し始め、社会の変質が進行する。2024/09/23
chang_ume
11
隋唐建国から盛唐を経て安史の乱以降に至る変遷を、都市史・女性史の視点を含みながら多面的に解きほぐしていく。この時代の概説入門書として今最良の一冊ではないかと思う。長安・洛陽の検討から、隋唐の「北族的色彩」を坊牆制などから見て取り、古代日本の都城系譜を考えるうえで一石を投じている。また対外関係について冊封体制と羈縻政策の連動を重視し、高句麗など周辺諸国の動向を新たな視点で理解していく。円仁の入唐体験のなかで新羅人コミュニティが果たした役割が、多文化社会としての唐を思わせるエピソードのようで味わい深く感じた。2021/08/20
さとうしん
10
通史としてシリーズ中最もオーソドックスな構成かつ内容。唐王朝では皇后が空位の期間が長いこと、それを皇太子の地位が不安定で、嫡長子相続の制度が確立しなかったのと結びつけて考えていること、外交面では吐蕃の位置づけに注目していることが特徴か。煬帝墓誌や吉備真備関係の石刻など近年の大発見も承けて、文庫版の補遺は他の巻より比較的充実している。2020/12/18
-
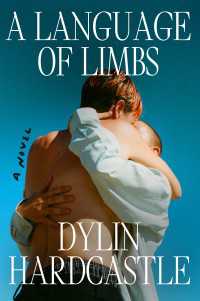
- 洋書電子書籍
- A Language of Limbs…
-

- 和書
- 図形と数が表す宇宙の秩序