出版社内容情報
いま小説に何が起きているのか?現場の思考を貫いた著者が、同時代の文学・批評と格闘してつかんだ、共に生きるための思想。
『テクストから遠く離れて』は、一見、難しそうに見える本だ。けれども、難しいのには理由がある。それは、ほんとうに大切なことだけれど、それをきちんと理解するためには、ぼくたちがふだん考えているような、「適当な」、あるいは、「みんなが考えているのでそうだと思いこんでいる」やり方では、ダメだ、という場合があるからだ。ときには、「堅い」ものを噛まなきゃならない必要がある。ぼくたちのからだに必要な「栄養」を与えてくれるものを、摂取するためには。
―ー高橋源一郎(「解説」より)
ポストモダン思想とともに80年代以降、日本の文学理論を席巻した「テクスト論」批評。その淵源をバルト、デリダ、フーコーらの論にたどりつつ、大江健三郎、高橋源一郎、村上春樹、阿部和重ら、同時代作家による先端的な作品の読解を通して、小説の内部からテクスト論の限界を超える新たな方法論を開示した、著者の文芸批評の主著。批評のダイナミズムを伝える、桑原武夫学芸賞受賞作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
amanon
6
「隠喩」や「換喩」といった基本的なタームをちゃんと理解しないまま読み進めたという体たらく。とりあえず、作者不在のテキスト論に対して、著者なりのスタンスを示したものと理解したがどうか?解説で高橋源一郎が示唆している通り、本書はかなり難解な部類に入るが、徒らに難解なロジックを弄んでいるのではなく、著者なりに当時の現代文学と深く対峙した上で、このようなテキストの紡ぎ出したのだと思う。個人的には『海辺のカフカ』の読解がとりわけ興味深かったか。中条章平による『カフカ』への辛辣な批評が印象的。その評価は変わったか?2022/12/06
なつのおすすめあにめ
2
『海辺のカフカ』目当てで読んだので「作者の死」云々については、難しいのであんまり理解できていない 笑 でもやっぱり『仮面の告白』は三島由紀夫しか書けないのだろうから……、なんて思うけどそう単純な話でもないらしい……。2021/06/07
Tommy
1
ポストモダン文学批評についての批判。歴史的経緯も説明されているのでわかりやすくはあるのだけど、構造主義とかの現代思想はフランス語が事態を余計にややこしくしている感。ところで。うまくいってないテクスト論批評の例として挙げられている渡部直己という文芸批評家、昔から批評が私情入ってる印象だったけど、数年前にセクハラで訴えられて失職してた。そういう人が作者と作品を完全分離するテクスト論者だったというのはなんかの寓話みたいだ。2025/04/21
Go Extreme
1
批評の視点と経験: 批評の必要性ー文学作品の解釈・テクストの現場性を失わずに理論化する→批評の視点 経験の重要性ーテクストの理解や批評 作者と作品の関係: 作者の死ー文脈を無視 読者ー作者の意図を理解する権利→新たな視点や解釈 読みの権利: 読者の役割ー独自解釈形成の権利 小説の構造ー読者を困惑≒は読者にとり挑戦 言語と表現の機能 ラカンの言語観ー浮遊するシニフィアン 虚構の重要性 文学批評の進化 社会との関係 文士と人間ー作家の個人的な経験や社会的な背景→テーマやキャラクター 文学の社会的役割2025/01/26
かいこ
1
(記憶が正しければ)蓮見重彦がたまに持ち出して来るような、テクスト読解を通して帰納的に生成される新たな「作者像」(大江的人物・古井的人物)概念に比べて、この人の提唱する「作者の像」概念はとりあえずテクスト読解に「作者」=発話者の項を作るために取り急ぎ考案した感じがしてあまり洗練されていないように思う。前者と後者では概念を持ち込んでくる批評的な狙いが多分違うから、「蓮見読んどけばいいじゃん」とは言わないけど、バフチンとか読んだほうがもっと有意義だと思った。 2020/12/24
-
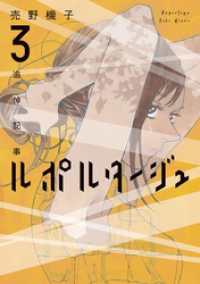
- 電子書籍
- ルポルタージュ‐追悼記事‐(3)
-

- 電子書籍
- 聖語の皇弟と魔剣の騎士姫 ~蒼雪のクロ…







