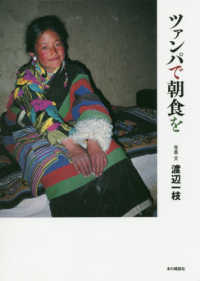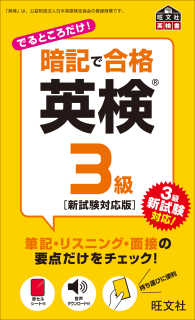内容説明
21世紀を迎えて20年、哲学の世界で大変動が起きている。問われているのは「人間以後」をいかに考えるか、である。『有限性の後で』のカンタン・メイヤスー(一九六七年生)、『四方対象』のグレアム・ハーマン(一九六八年生)、そして『なぜ世界は存在しないのか』で名を轟かせた一九八〇年生まれのマルクス・ガブリエル―。彼らが思考する「人間以後」とは「人間が消滅した後の世界」であるとともに「人間の思考が届かない場所」でもある。人類はどこに向かうのか?そして、何を考えればいいのか?若き俊英が大胆に提示する未来のスタンダード!
目次
プロローグ 「何をしたいわけでもないが、何もしたくないわけでもない」
第1章 偶然性に抵抗する―カンタン・メイヤスー
第2章 人間からオブジェクトへ―グレアム・ハーマン
第3章 普遍性を奪還する―チャールズ・テイラーとヒューバート・ドレイファス
第4章 新しい実在論=現実主義―マルクス・ガブリエル
エピローグ メランコリストの冒険
著者等紹介
岩内章太郎[イワウチショウタロウ]
1987年生まれ。早稲田大学国際教養学部卒業。同大学大学院国際コミュニケーション研究科博士後期課程修了。博士(国際コミュニケーション学)。早稲田大学国際教養学部助手を経て、早稲田大学、東京家政大学、大正大学ほか非常勤講師。専門は、哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
47
タイトルの「教科書」、「入門」はちょっとなあ。私にはかつて読んだガブリエル本の読み方がそれ程ズレてはいなかった事を確認できる参考書となりましたが…。原著にまったく触れてない方については参考書としてもちょっと…。/自然科学は意図的に考察の対象を事実に限定することで、人類史上稀にみる広範な客観性の創出に成功したのだ、と。私たちは生きるために認識するのであって、決してその逆ではない2022/09/10
ころこ
28
ポスト・モダンに対する理系からの懐疑に対して、思弁的実在論はカント以後の哲学を模索することでは一致しています。著者の見通しではマルクス・ガブリエルが高いのかも知れませんが、「意味の場」とはカント主義そのものであり、「世界」とはハイデガーそのものです。評価の難しいことを敢えて論じる意欲的な試みは買いますが、感心しないのは比喩によって誤魔化しがあるように読めることです。「高さ」と「広さ」の使い方こそが相関的ですし、マルクス・ガブリエルが最も「高さ」と「広さ」を取り戻そうとしているようにみえます。2020/11/03
無重力蜜柑
18
良著。この手の哲学はメイヤスー以外読んだことがなかったのだが、ガブリエルとかハーマンも読んでみようかと思う。ポモを乗り越える新実在論の哲学を「高さ」と「広さ」つまり超越性と普遍性の回復の試みと捉えて整理する。それが存在論や認識論といった形而上学的な議論(ガブリエルはこの用語法を否定するが)にとどまらず、意味や価値の擁護として個人の人生にも関わってくる。つまり実在論を通した実存論。全ては無価値という失望がニヒリズムだとすれば無価値が所与になってしまったメランコリーが現代の時代感覚という指摘は正しいと感じる。2022/10/01
evifrei
17
現代哲学の概要を示すのみならず、本書自体に深い哲学的洞察が感じられる。メランコリストについて書かれた部分は特に良い。生きていることに棒漠とした寂しさを感じた時には、本書を思い出す事になるだろうという予感と余韻をもって読み終えた。また、現代哲学を高さ(=神・憧れ) ・広さ(=普遍性)というスケールで捉え直すことで、各哲学の特色を具体的に把握しやすくなっている様に思う。(とはいってもやはりガブリエルの新しい実存主義は納得し難いものがあるけれど……。)恥ずかしながら押さえていなかったメイヤスーに興味が湧いた。2020/03/18
koke
12
哲学史の中に思弁的実在論を位置づけ、専門である現象学と比較し批判もしつつ、その新しさと意義がどこにあるのか指摘している。その際、思弁的実在論を実存論的に読んでいるのが面白い。メランコリストは、神のような絶対的な超越性にしか欲望が動かないという。著者がよく引き合いに出す『スカイ・クロラ』は私も2回観たが、1回目は感動して2回目は退屈した。私はどちらかというと著者が陽気な怪物呼ばわりするガブリエルに親近感がわく。テイラーとドレイファスにも共通する実在論+多元論という発想は「リアル」に感じられる。2023/12/27