出版社内容情報
観音、弥勒、地蔵、文殊・・・様々な姿を持った「悟りを求める人」。各尊の特徴と信仰の歴史を、図版をまじえて解説する仏教学入門。
内容説明
菩薩とは、自己中心の修行者ではなく仏の慈悲行を通して一切衆生を救おうとする修行者である。釈迦菩薩に始まり、大乗仏教の発展の中で、弥勒、観音、勢至など「十方世界」に多くの菩薩が修行につとめていると考えられるようになったという。二十以上におよぶ各尊の由来や役割、形像の特徴、日本への伝来と信仰の歴史を、写真や図版をまじえて解説。
目次
菩薩とはなにか
観音総論
観音各論
弥勒
文殊
普賢
虚空蔵
地蔵
その他の菩薩
著者等紹介
速水侑[ハヤミタスク]
1936年、北海道生まれ。北海道大学文学部史学科卒業。専攻は日本仏教史。北海道大学助教授、東海大学教授等を経て、東海大学名誉教授。2015年、没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
33
解脱して輪廻から離れた仏となるよりも、命あるまま六道(地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天)の遍く生物へ悟りの手を差し伸べる菩薩。様々なクライアントへ対応し(三十三の姿に変化)、願いの専門実務に携わるスペシャリスト(千手・弥勒・文殊・地蔵など)、時代が下がるにつれて、祈りの対象に特化&分化した菩薩が現れる。バラモン教から離れた仏教がヒンズー教と交応し、多肢多面の密教仏の特徴を備えていく。インドから伝わる中で中国化やメジャー化、逆に廃れていく菩薩も。写真も図版も多く、各寺の仏像の紹介等ハンドブックとしても重宝。2025/07/29
kawasaki
6
原著1982年。日本で信仰の対象とされている(された)菩薩たちの来歴、形象を一覧できる。半分くらいは観音とそのバリエーション。興味深かったのは、信仰が様々に変遷していく様。インドから中国・朝鮮を経ての変化、日本での時代ごとの変化など。「浄土教」が西方阿弥陀浄土に収斂する前の信仰、地蔵菩薩が道端の「お地蔵さん」になる過程などを知ることができる。2019/11/08
Ind
3
有名な菩薩について信仰の歴史がそれぞれわかりやすく解説されており、さらに詳しく知りたくなった。弥勒信仰が兜率上生と弥勒下生に分けられることを初めて知ったが、末法の世で来世に期待するだけでなく、弥勒が下生する現世に希望を持とうという考え方が面白いと思った。あと地蔵信仰が、現世で功徳を積むことができず来世は地獄行きだと絶望する庶民や没落貴族の間で広まったのも面白く、救済を願う歌の切実さに胸をうたれた。全体的に浄土思想の影響力の強さを感じ、歴史の中で信仰対象やその性質が変化する様子も興味深かった。2021/10/06
K子
0
仏像の中でも、日本あたりでは一番見る機会の多い、そしてバリエーションも豊富である菩薩にしぼって解説したもの。菩薩というのがそもそも大乗仏教の中で次第に信仰の対象とされてきたものですが、その数多い菩薩の来歴や特徴を説明しています。 講談社学術文庫だし、どちらかというと学術研究であり、その中では入門的な位置づけだと思います。菩薩像の特徴と来歴をバランス良く説明しているので、その役割は過不足無く果たしていると思います。 2020/03/30
-
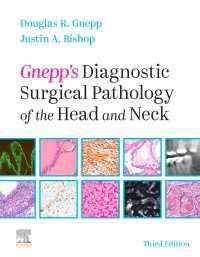
- 洋書電子書籍
-
頭頸部の診断外科病理学(第3版)






