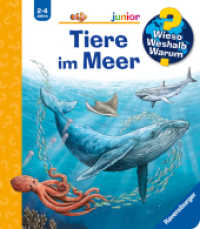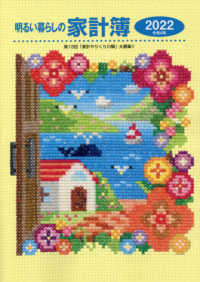出版社内容情報
平野 啓一郎[ヒラノ ケイイチロウ]
著・文・その他
内容説明
「カッコいい」を考えることは、いかに生きるべきかを考えることだ!「カッコいい」は、民主主義と資本主義とが組み合わされた世界で、動員と消費に巨大な力を発揮してきた。「カッコいい」とは何かがわからなければ、20世紀後半の文化現象を理解することは出来ない。それは、人間にポジティヴな活動を促す大きな力!
目次
第1章 「カッコいい」という日本語
第2章 趣味は人それぞれか?
第3章 「しびれる」という体感
第4章 「カッコ悪い」ことの不安
第5章 表面的か、実質的か
第6章 アトランティック・クロッシング!
第7章 ダンディズム
第8章 「キリストに倣いて」以降
第9章 それは「男の美学」なのか?
第10章 「カッコいい」のこれから
著者等紹介
平野啓一郎[ヒラノケイイチロウ]
1975年、愛知県蒲郡市生まれ。北九州市出身。小説家。京都大学法学部卒業。1999年、在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。著書に、『決壊』(第59回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞)、『ドーン』(第19回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞)、『マチネの終わりに』(第2回渡辺淳一文学賞受賞)、『ある男』(第70回読売文学賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
96
「カッコいい」について知りたい人におすすめの本になっている!「カッコいい」数値化できなくそして個人の主観で判断しがちなこの言葉について歴史やルーツ・関連ワードから少しずつ迫っていく話になっている。私たちはかっこ良くなりたいとかそれともカッコ悪くみられないようにしているのか。その議論については本当に面白くためになった!ルッキズムが未だに存在し美しいとされる人は加工等を使い現実離れをした美になる。それを私たちはアイドル化してしまう。YOASOBIの「アイドル」が流行る中色々と考えさせられた本であった!2023/08/25
クプクプ
64
私は幼少の頃、昆虫採集、ブラックバスのルアー釣り、プロ野球観戦をして育ったので特に音楽鑑賞には疎かったです。この本は著者がジャズのマイルス・デイヴィスのファンでジャズの歴史からロックの発達までを語ってくれたので大いに勉強になりました。また著者はすでに「本の読み方」がテーマの本を二冊出していますが、今作も海外の作家に触れているのでその三冊目と言えるでしょう。著者は「カッコいいとは果物のようなもので昨日は未熟で明日には腐ってしまうものだ」と書いていました。オスカー・ワイルドは弱者に優しかったという点で(続く)2020/08/21
シリウスへ行きたい
57
著名な小説家の本、エッセイか、なかなか面白い本である。日本人の好きな言葉、「カッコいい」を分析し説明している。私の孫も、「かわいい」といわれるより「カッコいい」といわれることを好むようになった。やはり男の子である。そのほうがいい、この前、会った時、少し顔に肉がついてきたので、「少し太ったな。」というと、ニコッと笑っていた。元気にあふれている、肉がついてきて、凛々しくなってきたという意味合い、それを感じてくれた。そのニュアンスが、全体として著者の意向にもあっている。男は、それが好きだ。男らしいとの評価だ。2023/11/04
koji
55
最近スポーツ、音楽、映画、本等痺れる場面に遭遇する頻度が上がった気がします。本書に言う「身体感覚に根差した共感によって人を導き、他者と結びつける」かっこいい感覚です。本書は、この「かっこいい」を歴史的、哲学的、カルチャー的に新書477頁を費やし分析していきます。途中の中弛みはありますが、納得の1冊でした。唯著者も言っているように「まだ序論」なんです。私の要望としても、「かっこいいと言われる側のマーケット戦略」、「『かっこ悪いが人生の幸福』という逆張り選択」等まだ分析してほしいテーマがあります。第二弾に期待2023/12/15
香取奈保佐
55
自分を絶えず突き動かしている「カッコいい」への憧れは何なのか。タイトルを見て即、レジに持って行った■エリートや識者に審美がゆだねられる世界と違い、カッコいいは感覚に働きかけてくる。著者は「しびれる」と表現するが、その感じの普遍性と絶対性ゆえに、人々はこれを猛烈に支持するのだ■ハッとさせられる指摘の数々。漠然とした心の領域に言葉や論理が入り込み、整えられていく。「『カッコいい』について考えることは、いかに生きるべきかを考えること」。こういう文章を書ける人に、自分は「しびれて」いるのだと改めて感じた。2019/11/24
-

- 電子書籍
- 異世界で孤児院を開いたけど、なぜか誰一…