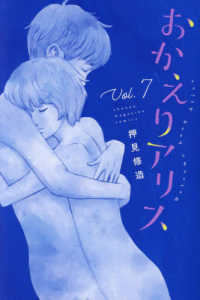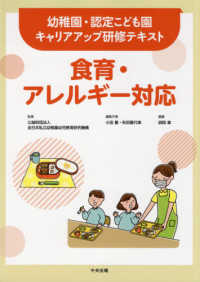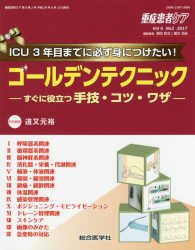出版社内容情報
「明後日の次の日」、あなたの町では何と言う?
「やのあさって」と答えたら、あなたは東日本の出身。「しあさって」と答えたら……?
さまざまな方言が列島に広がるさまを地図に表すと、そこから日本語の豊穣な世界が見えてくる!
国立国語研究所が総力を傾けて製作した『日本方言地図』をもとに、言葉がいかに伝播し、姿を変え、生成していくのかを描き出す。懐かしい言葉の記録でもあり、日本の長い歴史の探究でもあり、あたらな言葉の動態を探る探究でもある、無二の地図帳。
内容説明
「あさっての次の日」をあなたは「やのあさって」と言う?「しあさって」?自然・生活・感情・動植物など一七八語について、全国二四〇〇箇所の大規模調査をもとにして作られた言語地図を、明快な解説つきで一挙掲載。後世に残したい「お国ことば」の記録であり、言語の歴史の探究でもある、画期的「方言の読本」。日本語はこんなに豊かで面白い!
目次
第1部 自然(天地;月日・時間)
第2部 人間と生活(人倫;人体の名称など ほか)
第3部 動植物(動物;鳥 ほか)
音韻編((=)アイ
(=)ウイ ほか)
方言の基礎知識(方言の研究;東西方言の対立 ほか)
著者等紹介
佐藤亮一[サトウリョウイチ]
1937年東京生まれ。東北大学大学院博士課程単位取得。国立国語研究所名誉所員。フェリス女学院大学名誉教授。専攻は方言学、社会言語学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件