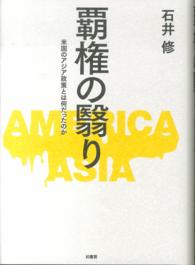出版社内容情報
幕末から明治にかけて、浮世絵はどのような終焉を迎えたのか。兄弟弟子の絵師の姿を通して描き切った、著者最高傑作の長編歴史小説!元治2年(1865)如月、清太郎の師匠で、義父でもある三代豊国の七七日法要が営まれる。三代は当代きっての花形絵師。歌川広重、歌川国芳と並んで「歌川の三羽烏」と呼ばれた。すでに広重、国芳を亡くし、歌川の大看板・豊国が亡くなったいま、誰が歌川を率いるのか。版元や絵師、公演者たちなど集まった弔問客たちの関心はそのことに集中した。清太郎には義弟の久太郎と、弟弟子の八十八がいた。久太郎は清太郎と同じく、門人から婿養子なった弟弟子。そして八十八は、清太郎より歳が一回りも下の弟弟子。粗野で童のような男だが、才能にあふれている。八十八が弟子入りしてすぐに三代はその才能を認め、挿絵を大抜擢で任せたりしたものだ。かたや清太郎が三代に褒められたのは、生真面目さしか覚えがない。その上、版元たちからは、三代の通り名「大坊主」を文字って、「小坊主」と呼ばれる始末。いったい、誰が「豊国」を継げようものか。清太郎は、苦い振る舞い酒を口へ運んだ──黒船騒ぎから12年が経ち、京の都には尊王攘夷の嵐。将軍さまは京に行ったきりと、徳川の世は翳りはじめていた。時代のうねりの中で、絵師たちは何を見、何を描き、何を残そうとしたのか!
一、梅が香の章
二、梅襲の章
三、裏梅の章
四、梅が枝の章
終 章
梶 よう子[カジ ヨウコ]
著・文・その他
内容説明
黒船来航から十二年、江戸亀戸村で三代豊国の法要が営まれる。広重、国芳と並んで「歌川の三羽烏」と呼ばれた大看板が亡くなったいま、歌川を誰が率いるのか。娘婿ながら慎重派の清太郎と、粗野だが才能あふれる八十八。兄弟弟子の二人が、尊王攘夷の波が押し寄せる江戸で、一門と浮世絵を守り抜こうとする。
著者等紹介
梶よう子[カジヨウコ]
東京都生まれ。2005年「い草の花」で九州さが大衆文学賞大賞を受賞。’08年『一朝の夢』で松本清張賞を受賞し、同作で単行本デビューを果たす(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
はたっぴ
のぶ
ぶんぶん
Fondsaule
タツ フカガワ