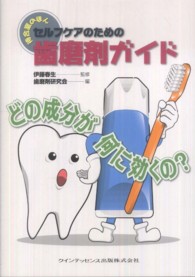出版社内容情報
アイルランドにはケルト人はいなかった! キリスト教以前のヨーロッパの基層をなした「幻の民」は、どこに住み、どこへ消えたのか?講談社創業100周年記念企画「興亡の世界史」の学術文庫版。大好評、第2期の4冊目。
ローマ文明やキリスト教以前の「最初のヨーロッパ人」はどこへ消えたのか? ストーンヘンジに代表される巨石文化、渦巻きや植物の華麗な装飾文様、妖精や小人などの伝説…「もうひとつのヨーロッパの起源」として、近年注目されている「ケルト文化」。EUなど欧州統合のアイデンティティとして、また近代西欧文明への批判として復興の気運をみせている「ケルト」の実像を、古代から現代にヨーロッパ史の中で明らかにする。
また、ケルト文化に関心を持つ多くの人々が訪れるのが、アイルランドである。それは、大陸からブリテン諸島へ移住した古代ケルト人は、ローマ人やキリスト教徒に追われてアイルランド島にのみしぶとく生き残った――と思われているからだが、最近の研究では、この「常識」が否定されつつあるという。本書では、言語学からみた「ケルト文化圏」と、歴史学からみた「ケルト人」の奇妙な関係を明らかにしていく。
そして、なぜ近代に「ケルト」は復興したのか? フリーメーソン、ナチスとの関係とは? 土着の文化は、ローマ文明やキリスト教とどのように融合し、広がっていったのか。言葉や文字は、そして文化は、いかに変容し、伝わるのか。ナショナリズムの興隆とともに語られる「民族起源としてのケルト」とは――。フランス、ブルターニュ地方の異教的な習俗や伝説の検証から始まる、異色の、そして初めての本格的「ケルトの歴史」。
[原本:『興亡の世界史07 ケルトの水脈』講談社 2007年刊]
はじめに とりあえず、ケルトとは何か
第一章 「異教徒の地」の信仰
第二章 巨石文化のヨーロッパ
第三章 古代ケルト人
第四章 ローマのガリア征服
第五章 ブリタニア島とアルモリカ半島
第六章 ヒベルニアと北方の民
第七章 ノルマン王朝とアーサー王伝説
第八章 ケルト文化の地下水脈
第九章 ケルトの再生
おわりに 結局、ケルトとは何か
学術文庫版のあとがき
参考文献
年表
主要人物一覧
索引
原 聖[ハラ キヨシ]
著・文・その他
内容説明
ローマ文明やキリスト教に覆われる以前に、ヨーロッパ文化の基層をなしたケルト人はどこへ消えたのか?巨石文化、異教的習俗と華麗な装飾文様、アーサー王伝説、フリーメーソンやナチスとの関係まで、古代から現代に至る異色の「ケルトの歴史」。フランス、ブルターニュ地方の歴史・信仰・言語を軸に、アイルランド中心のケルトブームを問い直す。
目次
はじめに―とりあえず、ケルトとは何か
「異教徒の地」の信仰
巨石文化のヨーロッパ
古代ケルト人
ローマのガリア征服
ブリタニア島とアルモリカ半島
ヒベルニアと北方の民
ノルマン王朝とアーサー王伝説
ケルト文化の地下水脈
ケルトの再生
おわりに―結局、ケルトとは何か
著者等紹介
原聖[ハラキヨシ]
1953年、長野県生まれ。東京外国語大学卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。現在、女子美術大学芸術学部教授。専門は近代言語社会史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
-





読書という航海の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
南北
イプシロン
やいっち
ルーシー
-
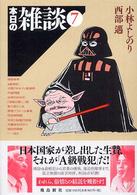
- 和書
- 本日の雑談 〈7〉