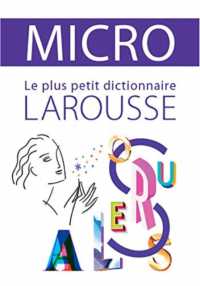出版社内容情報
互 盛央[タガイ モリオ]
著・文・その他
内容説明
「考える」あるいは「思う」という事象に主語はあるのか。「思われること」は本当に「私に思われ」ているのか。この問いに対する哲学者たちの近代以降の悪戦苦闘。ニーチェやフロイト、シェリングやフィヒテは、沈黙する「エス=それ」の淵源を見出したのか。「人」「言語」あるいは「普遍的なもの」とも呼ばれるものを巡る探求史。
目次
プロローグ―エスを奪い合う者たち
第1章 エスの問題圏
第2章 エスの淵源を求めて
第3章 変貌するエス
第4章 エスへの抵抗
エピローグ―「エスの系譜」のゆくえ
著者等紹介
互盛央[タガイモリオ]
1972年、東京生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。言語論・思想史。現在、講談社勤務。著書に『フェルディナン・ド・ソシュール』(作品社。和辻哲郎文化賞、渋沢・クローデル賞)、『言語起源論の系譜』(講談社。サントリー学芸賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mstr_kk
11
すばらしい本でした。フロイトの「エス」はどこからどのように伝わってきたのか、同時代・のちの時代の中でどのような位置と意義をもつのかという、僕の知りたかったことをドンピシャでやってくれているのもありますが、とにかく文章がいい。まるで映画を観るように、場面が鮮やかに浮かぶ文章です。そして情報量がすさまじい。よくこんな大量の情報を、こんな簡潔な文章でさばきつづけられるものです。めちゃくちゃ勉強になりました。ただ、途中消化しきれていないところもあるので、また精読したいと思います。2016/10/21
t_m_r
4
二つのエスの系譜をたどる中で、フロイトがこだわった両者の峻別が、神秘主義やファシズムの批判と連関していたことがやがて明らかとなる過程はスリリング。解説でマルクスの不在について指摘されているが、同様にエピローグでメルロポンティ、レヴィストロース、ドゥルーズを扱いつつラカンにはほぼ触れていないのも奇妙。著者が批判的な第二のエスの系譜は、マルクスでいえば物象化、ラカンだとファルス、超越論的シニフィアンの問題系と関わるように思われる。著者自身がエスに導かれて対象の選別を行っているように読める点も興味深かった。2017/01/23
brian.fabu
3
「エス」の系譜をまとめて行く作業の手際よさは圧巻。語る主体を持たないはずのエスは、時代の潮流と共に、我有化され神だの、私だのが挿入されていく。 自分が読み取ったこととしては、ハイデガーが存在者と存在と間に設けた存在論的差異を、フロイトの心的局所論の一審級エスについての考察へと結び付けているというような印象。このように考えるとたしかにフロイトの謎めいた著作『モーセ』が明らかになるように思われた。本書でも引かれるフロイトの引用を一つ。 「神秘主義とは、自我の外部の領域であるエスのぼんやりとした自己知覚である」2018/03/27
huchang
2
感想を書きたいのに、言葉がうまく出てこない。良かったんだが、こう、あるだろう?もっと著者に敬意を表すいい言葉が…という感じ。圧巻、というにふさわしい内容だった。意識を扱うのに必ず出てくる名前はもちろんのこと、ブラヴァツキーまで出てくるの?どんだけ情報の手綱さばきが上手いんや…と何度も五体投地したくなった程度には素晴らしい。しかも文章もタイトルもいい。2020/12/21
μέλισσα
1
最後にドゥルーズが現れながらもカントはほとんど出てこない、超越論的主観性と前個体的な超越論的領域との差、おそらくは更に、超越論的主観性とデカルトの実体的なコギトとの差、この私には明確に言語化できない、しかし非常に大きな問題が眠っている気がする。 故に、きっとまた読むことになるのだろう。 私には今はまだ評価できないはず2025/06/04