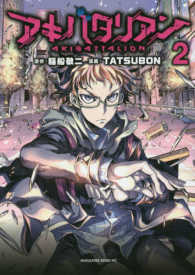出版社内容情報
魚食文化、冠婚葬祭のしきたりや神事・祭礼、魚に関する信仰や呪術まで、魚と日本人の生活誌を扱う、類書のない、楽しい本。世界一の好魚民族である日本人。魚と日本人の生活誌を扱おうとした試みとして、本書は類書のない、楽しい書物である。魚の故事、魚食文化をはじめ、冠婚葬祭のしきたりや神事・祭礼、魚に関する信仰や呪術まで、誰でも思い当たる生活に溶け込んだもの、意表を突く珍しい事例をたっぷりと挙げ、暮らしの中のさまざまな日本の慣習、民俗などが、こんにちも魚によって支えられているということをくり返し実証する。また、著者は伊勢神宮に奉職する神官であったため、一般の目に触れることの少ない伊勢神宮における魚の扱い方など、神社仏閣の式典の折にささげられる魚の話題は詳しく、興味深い。
第一章 日本人と魚
一 魚食のあこがれ
二 魚食の民族
三 初穂と初尾
四 食い初めには魚
五 神饌の魚
第二章 魚のシンボル
一 仏さまの足に魚
二 めでたい双魚紋
三 掛鯛と懸魚
四 天と地の魚
第三章 生臭の文化
一 「のし」つけて
二 伊勢神宮とアワビ
三 中国の玉ぎよくとアワビ
四 精進落しの魚
五 「晴の日」の魚
六 食用以外の魚の利用
第四章 魚の民俗
一 魚の祭り
二 お寺と魚
三 魚の魔除け
四 魚の供養と雨乞い
五 イワシの念仏
六 タイと南天の葉
七 イカと寿留女
八 タコ神とタコ薬師
九 オコゼと山の神
一〇 サバ大師とサバの道
第五章 魚の文化誌
一 アユで占い
二 コイのアイディア
三 エビの蓬莱飾り
四 カツオ武士
五 ウナギと山の芋
六 ひょうたんナマズと地震
七 ハマグリと女性
八 珍魚と毒魚
九 サメと日本刀
一〇 エイと文化財
あとがき
魚の文化史年表
矢野 憲一[ヤノ ケンイチ]
著・文・その他
内容説明
世界一の好魚民族といわれる日本人が魚とともに生きた生活誌を扱う、ユニークな著。魚に関する文化的知見が満載。楽しい魚の民俗学。
目次
第1章 日本人と魚(魚食のあこがれ;魚食の民族 ほか)
第2章 魚のシンボル(仏さまの足に魚;めでたい双魚紋 ほか)
第3章 生臭の文化(「のし」つけて;伊勢神宮とアワビ ほか)
第4章 魚の民俗(魚の祭り;お寺と魚 ほか)
第5章 魚の文化誌(アユで占い;コイのアイディア ほか)
著者等紹介
矢野憲一[ヤノケンイチ]
1938年三重県生まれ。神宮皇学館神道研習科、国学院大学文学部日本史学科卒業。伊勢神宮に奉職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
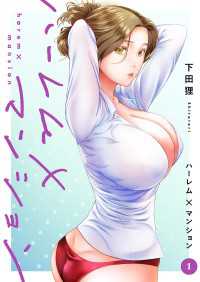
- 電子書籍
- ハーレム×マンション【電子単行本版】1…
-
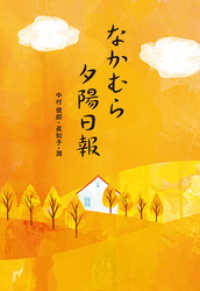
- 電子書籍
- なかむら夕陽日報