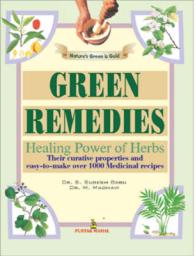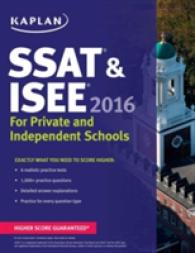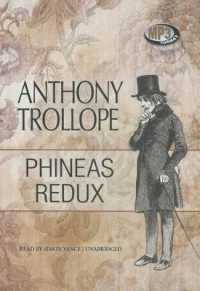出版社内容情報
高橋 哲哉[タカハシ テツヤ]
著・文・その他
内容説明
ポスト構造主義を代表する哲学者、ジャック・デリダ。ロゴス中心主義が「まったき他者」を排除・隠蔽してきた歴史を暴き出した尖鋭で長大な問いかけは、現代に影響を与え続けている。脱構築、散種、差延をはじめとする独創的な概念を生み出した思想の核となる「哲学的」モチーフをとらえ、「他者との関係としての正義」を潜在的・顕在的に追究する。
目次
第1章 砂漠のなかの砂漠
第2章 形而上学とは何か
第3章 言語・暴力・反復
第4章 法・暴力・正義
第5章 メシア的なものと責任の思考
主要著作ダイジェスト
キーワード解説
読書案内
著者等紹介
高橋哲哉[タカハシテツヤ]
1956年生まれ。東京大学教養学部教養学科フランス分科卒業、同大学院人文科学研究科博士課程単位取得。専攻は哲学。東京大学大学院総合文化研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
30
『パイドロス』にある「プラトンのパルマケイアー」を引いてパルマコンとエクリチュールの関係を展開させている第2章が秀逸です。パルマコンが哲学者か魔術師か分からないソクラテス(父)を殺すのですが、このパルマコンとは薬であって同時に毒である決定不可能な存在です。父の不在性、決定不可能性は、一旦文脈を離れるとその意味はAにもなり非Aにもなり得るという観点ではエクリチュールの問題とパルマコンは同義です。現前の言葉(ソクラテス)であるパロールと不在の言葉(プラトン)であるエクリチュールの二項対立において、実はパロール2020/10/25
またの名
14
仮名で本を書いたキルケゴールの話が他者への絶対的責任を果たすのに必要な無責任の例だと言われると、ネットの匿名性は何なのか気になって謎。少なくとも著者がデリダに認めるアポリアは、他者を語ることで応答責任を遂行する身振りが実は言語等で共有できる一般性に他者を還元する暴力と常に表裏一体であるため、単純に他者万歳を唱えれば片付く問題ではないのが肝。パロールが威張ってるのでエクリチュールを持ち上げようとか、法は脱構築可能だけど正義は脱構築不可能だから最強とか考えるだけでは済まないことを思い知らされる、倫理的な解説。2015/12/24
なっぢ@断捨離実行中
13
再読。よくここまで噛み砕いて説明できたな、という印象。スピヴァクのあの晦渋な序論とは天と地ほどの差がある。まとまったデリダ入門書は本書と仲正のくらいしかないので大変有り難いのだが、デリダの思想をパフォーマティブに示せているか、と問えば当然否。しかし、言語の不可避的な暴力性を著者は充分自覚し「最小の暴力」にコミットしているので若干の戸惑いを感じつつも評者は「ウィ」と応じたい。デリダが今後とも読まれるにはこんな優等生的なデリダ像も、著者のような凡庸な教師も必要なのではないか。他者への責任を果たすためにも。2017/03/14
masabi
8
【概要】デリダの半生、脱構築を中核に据えた思想を解説する。【感想】デリダの文章自体がパフォーマンスに満ちていて難しい。プラトンのテクスト読解に始まり脱構築を解説するが、その内実は一貫して他者の痕跡をすくい上げ、他者への応答に責任を負っているとする。言説や決定の暴力性を自覚しつつも、なお決定しなければならない決定の思想である。本書ではプラトンと聖書のイサク奉献が取り上げられているが、他にも様々な文学作品で同様に脱構築的解釈を繰り広げ、それが文学理論にも波及した。次は文学理論のほうの脱構築の解説書を読みたい。2024/04/27
Happy Like a Honeybee
8
法は脱構築可能だが、正義は脱構築不可能か?デリタの生涯を時系列で展開する内容。哲学、言語、法・政治、宗教など…。基礎知識があり、様々な解釈を必要とする人向け。読み手を選択するような。私は第三章あたりから厳しかったが、挑戦する姿勢が重要2016/07/18