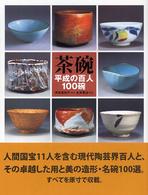出版社内容情報
日本史の中で最も激しく社会が動いた時代。
室町幕府の権威の失墜、荘園公領制の変質と、中世社会の中央集権的な性格が崩れ始める。民衆が自立性を強め守護や国人が戦国大名へと成長する時代の動きを分析。
久留島 典子[クルシマ ノリコ]
著・文・その他
内容説明
応仁・文明の乱を機に未曾有の「地殻変動」に曝される中世社会。室町幕府の権威は失墜し始め、荘園公領制も変質してゆく。集権的性格が薄れるなか、民衆は村や町を拠点にどう自立性を強めていったのか。また守護や国人たちはいかにして戦国大名へと成長したのか。あらゆる階層で結ばれた「一揆」に着目、史上最も激しく社会が動いた時代を分析する。
目次
第1章 領主の一揆―戦国大名の登場
第2章 百姓の内と外―村と村々
第3章 家中の形成から合従連衡へ―西と東の戦国大名
第4章 家中と国家―領国の仕組み
第5章 都市と都市民
第6章 戦乱に生きる
終章 戦国の収束
著者等紹介
久留島典子[クルシマノリコ]
1955年生まれ。東京大学大学院博士課程中退。現在、東京大学史料編纂所教授。日本中世史専攻。中世武家文書の編纂に従事しながら、中世から近世への社会の転換の特質を明らかにするために、村落史や領主制の研究をすすめている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
100
この時代もあまり詳しく読んだ本はあまりないので、じっくり読むことができました。私はこの中では、経済的に書かれていたところが好きで、村や百姓について書かれたところや都市と都市民についてのところが楽しめました。このシリーズは著者によって書かれている主題が変わるので時たまいいものが掘り当てられます。2017/06/23
coolflat
13
45頁。氏綱は名字を「伊勢氏」から「北条氏」に変えた。なぜ「北条氏」なのか。それは鎌倉幕府の執権を世襲した北条氏が、代々相模守に任じられ「相模太守」を名乗ったからである。力で相模を奪取したとはいえ、関東の諸氏から相模の正統な国主として認められていなかった氏綱が、北条氏の名字を名乗り、自らを鎌倉北条氏に擬することで、正統な相模の支配者たる立場を主張したのではないかと指摘されている。そしてその狙い通りに、北条氏は相模のみならず、関東における正当な支配者「公儀」への道を歩んでいくのである。2023/06/04
かんがく
12
戦国大名、一揆、惣村、職人、伊勢参宮などについて分析を加え、戦国時代を「帰属の一元化」として捉える。戦闘における人身売買、領国内での貨幣流通など、普通はあまり触れられないところも詳しく書かれており、近世へ繋がる時代としての戦国時代がよくわかった。2019/03/24
閑
9
応仁の乱収束から信長の上洛まで。主に戦国時代前半期、信長世代の祖父・父親が活躍の中心。ただ記述は戦国大名たちの合戦・外交史よりも、戦国時代の基盤となった村・都市の社会の仕組、都市における貨幣経済、大名の「家中」の形成などのほうに大部分を割いている。戦国武将の華々しい絵巻を期待していると正直肩透かしを食らう内容だが、学問としての日本史だからしょうがない。家中の成立・戦国家法の制定・楽市令を始めとする経済政策など信長世代の戦国大名家の基盤が出来ていく感じが印象に残った。2015/02/14
sibasiba
8
戦国時代前半戦には不案内なのでその辺りを期待したが、このシリーズで期待するものではなかった。一応その辺も記述は有るのだがていうかメインの筈だが。ココ数巻を読んで今巻も徳政の話が印象に残った。撰銭の話なども面白く、東西での銭の好みの違いや金が主流の東と銀が主力の西とか通貨についてまた別の本も読んでみよう。2013/07/28
-

- 電子書籍
- 少女マンガのヒーローになりたいのにヒロ…
-
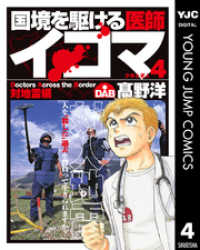
- 電子書籍
- 国境を駆ける医師イコマ 4 ヤングジャ…