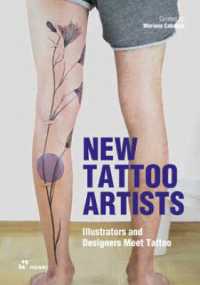出版社内容情報
日本的古典文化の誕生と藤原氏の栄華の時代 日記や古文書の精緻な解読により政治・財政・文化等、古代の国家システムを解明。中国文明との交流も射程に収め探究する、美と権勢を極めた貴族政治の合理性とは
大津 透[オオツ トオル]
著・文・その他
内容説明
平安時代中期、『源氏物語』や『枕草子』など、すぐれた古典はどうして生まれたのか。栄華を誇った藤原道長はどのように権力を掌握したのか。貴族の日記や古文書の精緻な読解によって宮廷を支えた古代国家のシステムを解明、日本の古典文化の形成に重要な役割をはたした中国文明との交流に迫る。貴族政治の合理性を鮮やかに描く平安時代史研究の劃期。
目次
第1章 道長の登場(摂関制度の変遷;兼家とその子息 ほか)
第2章 一条朝の名臣と貴族社会(日記を記す貴族;小野宮右大臣実資 ほか)
第3章 宮廷社会を支えたもの(受領支配の成立;受領の役割と任官システム ほか)
第4章 王朝の文化(神事と祭;仏教と法会 ほか)
第5章 道長のあとに(三条天皇から頼通の時代へ;受領支配と国家財政の変質)
著者等紹介
大津透[オオツトオル]
1960年生まれ。東京大学大学院修士課程修了。東京大学准教授。専攻は日本古代史、唐代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
136
この巻はまさしく専門書ですね。これだけ細かく詳しいと一般的な歴史の本ではない感じです。私は今まで中公版や小学館版での日本歴史全集を読んでみていますが、この時代をこれだけ詳細に分析している本は見当たりません。歴史を楽しむというよりも姿勢を正して歴史の勉強をするというイメージです。それはそれで私は嫌いではないのですが一般受けはしないでしょうね。2017/04/03
coolflat
17
藤原摂関政治全盛の時代。主に藤原道長・頼通を扱う。20頁。藤原道長の曽祖父にあたる忠平の時代こそが、摂関体制の成立期であると位置づけられ、以下の三点があげられる。第一は、摂政と関白が制度的に定着したこと。天皇大権を代行する摂政と、天皇の補佐である関白の差が制度化され、天皇幼少の間は摂政をおき、成年後はあらためて関白になすパターンが成立した。第二は、儀式・故実の成立。調停での儀式の具体的な作法故実が成立し、朝廷儀礼の標準型が形成されたのが、忠平の時代であった。第三は、摂関政治を支える貴族連合体制の成立である2020/07/16
かんがく
15
そうとう歴史好きでないと退屈に感じる、平安時代の貴族の官職や職務内容の話が続く。ただ、これは『栄花物語』に見られるような、藤原家中心の華やかな平安イメージを覆そうという挑戦である。『小右記』などの日記を豊富に用いて、藤原氏の現実を描いていく。ただ、どうしても描写が細切れで物語が見えず、集中が続かないところもあった。2019/05/14
sibasiba
9
華やかな宮廷文化、といってもみんな働いてます。源氏物語みたいに和歌と女遊びがお仕事ではないのです。今巻は道長は立派な政治家で別に天皇を傀儡とした訳ではなく協力して政治をしていたよ、気に入らない后に嫌がらせしたり後継者選びも自分が決めて主導権大体こちらにあるけど、という内容。興味深いのが日記を細かくつけて政務の記録として家に残した事。切り貼りしたり書き写したり、更には売り買いしたり現代の日記とはかなり違う。2013/07/02
閑
7
題名どおり摂関期、具体的には道長登場から死までが8割5分、残りが頼通の時代。教科書で習ったよりも摂政・関白(+内覧)という制度が複雑でただ摂関の座につけば権力が掌握できるというわけではなく、道長という敏腕政治家によって権力の集中が進められた過程が叙述されている。「この世をば~」の歌のように専制的に振舞っていたわけでもなく一級の政治家としてこの時代を形作った道長像が印象的だった。日記等資料が多いせいか全体的に相当細かいところまで踏み込んで書かれているので読みづらい部分も多いのが玉に瑕な感じ。2014/05/06