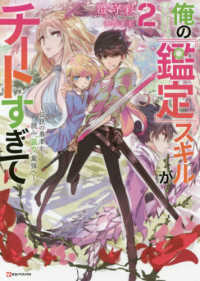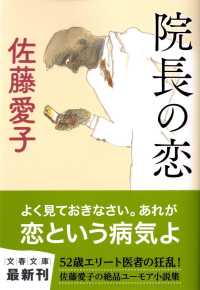出版社内容情報
折口信夫の対話集。文学は北原白秋、川端康成、小林秀雄等と、民俗学は柳田国男等と、仏教・神道は鈴木大拙等との対談・鼎談を編纂。折口が語り合った日本の叡智たち。川端、犀星、小林秀雄、柳田国男、鈴木大拙……。
全集未収録も所載。
折口信夫の対話集。文学は北原白秋、川端康成、小林秀雄等と。民俗学は柳田国男等と。仏教・神道は鈴木大拙等との対談・鼎談を編纂。
※本書は中央公論新社『折口信夫全集』別巻3(1999年9月刊)、「鶴岡」第15号(1943年9月刊)、「悠久」第4号(1948年10月刊)を底本としました。
1 文学をめぐって
緑ケ丘夜話(×北原白秋)
古典について(×室生犀星)
一九四九年の春を語る(×西脇順三郎)
細雪をめぐって(×川端康成、谷崎潤一郎)
日本詩歌の諸問題(×神西清、日夏耿之介、三好達治)
古典をめぐりて(×小林秀雄)
燈下清談(×小林秀雄)
2 民俗学をめぐって
日本人の神と霊魂の観念そのほか(×柳田国男、石田英一郎)
民俗学から民族学へ(×柳田国男、石田英一郎)
3 神道学をめぐって(全集未収録座談会)
思想維新──まつりに就いて(×『鶴岡』同人)
神道と仏教(×鈴木大拙、横山秀雄、『悠久』同人)
折口 信夫[オリクチ シノブ]
著・文・その他
安藤 礼二[アンドウ レイジ]
編集
北原 白秋[キタハラ ハクシュウ]
著・文・その他
室生 犀星[ムロオ サイセイ]
著・文・その他
西脇 順三郎[ニシワキ ジュンザブロウ]
著・文・その他
三好 達治[ミヨシ タツジ]
著・文・その他
川端 康成[カワバタ ヤスナリ]
著・文・その他
小林 秀雄[コバヤシ ヒデオ]
著・文・その他
柳田 国男[ヤナギダ クニオ]
著・文・その他
谷崎 潤一郎[タニザキ ジュンイチロウ]
著・文・その他
神西 清[ジンザイ キヨシ]
著・文・その他
日夏 耿之介[ヒナツ コウノスケ]
著・文・その他
石田 英一郎[イシダ エイイチロウ]
著・文・その他
今泉 源吉[イマイズミ ゲンキチ]
著・文・その他
高佐 貫長[タカサ カンチョウ]
著・文・その他
座田 司氏[サイダ モリウジ]
著・文・その他
鈴木 大拙[スズキ ダイセツ]
著・文・その他
横山 秀雄[ヨコヤマ ヒデオ]
著・文・その他
和歌森 太郎[ワカモリ タロウ]
著・文・その他
小野 祖教[オノ ソキョウ]
著・文・その他
内容説明
生涯に膨大な対談、鼎談を残した折口の対話を三章で構成した安藤礼二のオリジナル編集。北原白秋、室生犀星、西脇順三郎、谷崎潤一郎、川端康成、小林秀雄達と文芸を語り合った第一章。第二章は師・柳田国男と民俗学について。鈴木大拙等との宗教をめぐる第三章は、全集未収録で資料としても貴重な座談会である。
目次
1 文学をめぐって(緑ケ丘夜話(×北原白秋)
古典について(×室生犀星)
一九四九年の春を語る(×西脇順三郎)
細雪をめぐって(×川端康成、谷崎潤一郎)
日本詩歌の諸問題(×神西清、日夏耿之介;三好達治)
古典をめぐりて(×小林秀雄)
燈火清談(×小林秀雄))
2 民俗学をめぐって(日本人の神と霊魂の観念そのほか(×柳田国男、石田英一郎)
民俗学から民族学へ(×柳田国男、石田英一郎))
3 神道学をめぐって(全集未収録座談会)(思想維新―まつりに就いて(×『鶴岡』同人)
神道と仏教(×鈴木大拙、横山秀雄、『悠久』同人))
著者等紹介
折口信夫[オリクチシノブ]
1887・2・11~1953・9・3。歌人、詩人(歌人、詩人としては釈迢空を名乗った)、国文学者、民俗学者。大阪生まれ。1910年、国学院大学卒業後、中学校教師を経て、国学院大学、慶応大学で教鞭をとる。島木赤彦、柳田国男との出会いで歌誌「アララギ」、民俗学雑誌「郷土研究」と関わることとなり、その後の生涯が決定づけられる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
井月 奎(いづき けい)
chanvesa
1.3manen
roughfractus02
うえ