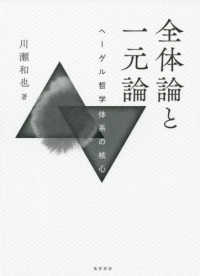出版社内容情報
暮らしの中の「超宗教」
歴史と伝統に磨き抜かれ、私たちの生活を支える神道に関する素朴な疑問をズバリ解明
私たちの暮らしの中には、神道に由来するものがたくさんあります。神道は古来、私たちの生活と人生を支えてきた「超宗教」といえます。祝儀でなぜ水引を使うのか/相撲でなぜ力士が塩をまくのか/「水に流す」とは何を流すのか/お神輿を褌一丁でかつぐわけ/伊勢の神宮はなぜ白づくめなのか/柏手はいくつ打つのが正しいのか、など多くの人が日本の神道、神社について抱く素朴な疑問に対して、ずばり解説した、神道がすぐに理解できる本。
●産土神は人の世をすべて見ている
●「みそぎ祓い」で「物の気」が浄まる
●なぜ神様へのお供物に塩が必要なのか
●なぜ神社には玉砂利を敷くのか
●柏手はいくつ打つのが正しいのか
※本作品は、1991年11月に日本文芸社より刊行された単行本を文庫収録にあたり加筆、改筆したものです。
山蔭 基央[ヤマカゲ モトヒサ]
著・文・その他
内容説明
私たちの暮らしの中には、神道に由来するものがたくさんある。神道は古来、私たちの生活と人生を支えてきた「超宗教」といえる。祝儀でなぜ水引を使うのか/相撲でなぜ力士が塩をまくのか/「水に流す」とは何を流すのか/お神輿を褌一丁でかつぐわけ/伊勢の神宮はなぜ白づくめなのか/柏手はいくつ打つのが正しいのか、など多くの人が日本の神道、神社について抱く素朴な疑問に対して、ずばり解説した、神道がすぐに理解できる本。
目次
第1章 日本人の神道観(土を離れ天を仰ぐようになった日本人;金ピカ仏にだまされた古代の権力者;策略なき素直さを失った日本人 ほか)
第2章 巷の神道を探る(神道にかかわる塩の話;神道にかかわる水の話;知っておきたい寺と神社の違い)
付録 神道祭事の手びき(神社参拝の手びき;地鎮祭(起工式)の手びき
神葬祭の手びき ほか)
著者等紹介
山蔭基央[ヤマカゲモトヒサ]
1925年、岡山県生まれ。皇典講究所に学ぶ。肺結核を患い仮死状態に入り、異次元世界を体験した後、奇蹟的快復をみる。その後、神道修行に入り家学を修め、1949年、明治天皇外戚家の中山忠徳の猶子として、応神朝以来伝承する山蔭神道家第79世を相続して、古神道の体験的研究と学問的研究を行う。また1960年には、亜細亜大学で近代経済学を学び、古道と科学の両面を研修する。その後、宗教法人山蔭神道を愛知県に設立し、管長に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
熊童子
カツ
Kohei Fujimoto
踊られ念仏
R
-
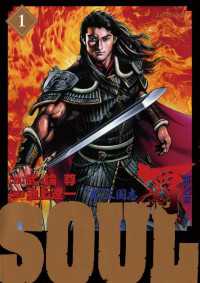
- 電子書籍
- SOUL 覇 第2章(1) ビッグコミ…