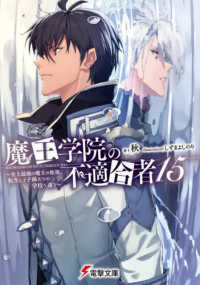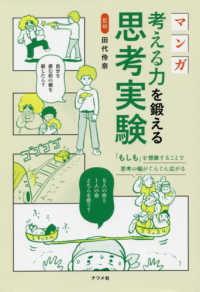出版社内容情報
馬駆ける草原に興った、もうひとつの文明 黒海北岸のスキタイ、モンゴル高原の匈奴。「蛮族」とみなされた彼らが築いた広大な国家と、独自の文明とは。ヘロドトスや司馬遷が描いた騎馬遊牧民の世界を探る
第1章 騎馬遊牧民の誕生
第2章 スキタイの起源
第3章 動物文様と黄金の美術
第4章 草原の古墳時代
第5章 モンゴル高原の新興勢力
第6章 司馬遷の描く匈奴像
第7章 匈奴の衰退と分裂
第8章 考古学からみた匈奴時代
第9章 フン族は匈奴の後裔か?
林 俊雄[ハヤシ トシオ]
著・文・その他
内容説明
前七世紀前半、カフカス・黒海北方に現れたスキタイ。前三世紀末、モンゴル高原に興った匈奴。彼らはユーラシアの草原に国家を築き、独自の文明を作り出した。ヘロドトスや司馬遷が描いた騎馬遊牧民の真の姿は近年の発掘調査で明らかになってきた。
目次
第1章 騎馬遊牧民の誕生
第2章 スキタイの起源
第3章 動物文様と黄金の美術
第4章 草原の古墳時代
第5章 モンゴル高原の新興勢力
第6章 司馬遷の描く匈奴像
第7章 匈奴の衰退と分裂
第8章 考古学からみた匈奴時代
第9章 フン族は匈奴の後裔か?
著者等紹介
林俊雄[ハヤシトシオ]
1949年、東京都生まれ。東京教育大学卒業、東京大学大学院人文科学研究科博士課程東洋史学科単位取得退学。古代オリエント博物館研究員を経て、創価大学文学部教授。専門は中央ユーラシアの歴史と考古学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ピオリーヌ
14
まえがきで著者が「それまで軽んじられてきた遊牧の文明だが、本シリーズでは全二十一巻のうち、三巻分が遊牧の文明に当てられている」と書くように、スキタイと匈奴に一冊分割かれている事は快挙だといえる。フィリッポス二世と激戦を繰り広げたアタイアス、漢から匈奴に仕えた宦官で、ディベートに優れた中行説等魅力あふれる人物が登場。内容も考古学的見地が多く取り入れられ、大満足。2020/04/25
羊山羊
13
今回は遊牧民族を主に、古代中国との関わりに焦点を当てながらその発掘史を紹介しつつ遊牧民族を語るスケールの大きな1冊。盗掘によって奪われた遺産の多いことと言ったらない。古代中国と言いつつ、遊牧民族はヨーロッパ方面にも影響を与えていたので、ヘロドトスの名前も出てくる。定住地と言う考えが希薄な彼らが歴史に刻んだその中に触れる一冊。2020/12/24
電羊齋
13
文献史料と考古学的成果を交え、牧畜と馬の家畜化の起源から始まり、ユーラシア規模の広がりを持つスキタイとその多様な文化、そして匈奴の歴史、社会、文化、定住集落などを概説。そして「匈奴・フン同族説」を取り上げつつフンの歴史と文化も紹介。スキタイと匈奴など各遊牧騎馬民を比較対象する視点も興味深かった。文章も読みやすく、半日で一気に読んでしまった。面白い!2020/01/04
りー
13
世界史門外漢がいざ学び始めようとしたら、「世界史」=西側諸国+イスラム+中国、という範囲で捉えている本が多くて。いやいや、その中間に広がる広大な土地は?という疑問に応えてくれそうなシリーズです。この巻の著者が、最近になってやっと騎馬遊牧民再評価の機運が高まってきたとしみじみ書いているので、新しい視点なんだなーと。スキタイに関してはヘロドトス以外はほぼ考古学的な内容で、匈奴は「史記」「漢書」と考古学両方から。これからもっと研究が進んでほしい分野。とりあえず、騎馬遊牧民族関連の巻だけでも読破したいと思います。2019/03/10
六点
13
このシリーズにハズレはなく、常に蒙を開かれっぱなしである。天山山脈から始まりパンノニア平原に至るまで続く草原の道がユーラシアの歴史を動かしてきた事を、考古学、文献史学を通じて解き明かされる。政治的に極めて敏感な部分をはらみ続けてきた遊牧の文明の歴史は、日本人にとっては縁遠いものの、ある意味政治的立場から自由になれる強みを持っていると言えよう。また、トゥルクの世界の広がりと分断は宗教の影響が大きいことがわかる。イスラム以前の無明時代の豊穣さにトゥルクが目覚めた時、また世界は大きく動くのでは無いかと妄想した。2018/06/01