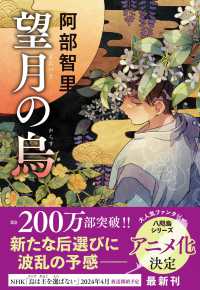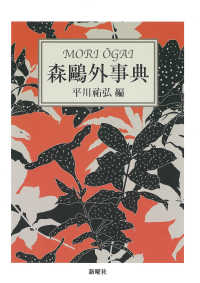内容説明
類稀な審美眼、研ぎ澄まされた美意識は、どのようにして形成されたのか。能に始まり、骨董、茶道、生け花、きものなど日本の古典文化への造詣を最高点まで追求していくさまは、人生に確たる物差しを持つことの大切さを示してくれる。生き方の達人・白洲正子の生涯を通して、日本人が失ったものを問いかける。
目次
白洲正子をとらえる旅
能から学んだこと
骨董に遊ぶ
お茶、生け花、そしてきもの
「いにしへ」を旅する
有用の人たるべし
著者等紹介
馬場啓一[ババケイイチ]
1948年、福岡県生まれ。早稲田大学法学部卒。CMディレクターを経て、現在、作家・エッセイスト
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うりぼう
42
ブックオフで購入。もうこうした女性は、生まれない。才女と呼ばれる女性は数多いますが、彼女の生き方は、全く違う感覚。「能」をベースに日本文化を感じ、語る。その道の専門家でさえも、凌駕する博識と独特の知見を持ち、とにかくカッコイイ。男前なのだ。「和すれども同せず」が日本文化の特質と語り、「宇宙の中にとけこんで、宇宙と一体となった」境地が西行。その西行に生きようとした正子。骨董も花も茶も、着物、旅、全てが自分と渾然と一体化し、でも完成形とならない世界観。「よびつぎ」が、地元、名古屋の地名にあることを誇りに思う。2012/07/09
めぐたん
1
西行に興味をもった2014/11/01
ナウラガー_2012
0
正子の母(常子)は「きもの」に詳しく「香」を聞く趣味、「茶道・華道」にも通じていた/正子にとっての理想の茶碗は長次郎の「無一物」志野の「卯花墻(ウノハナガキ)」「高麗の井戸の茶碗」/現代の茶道は女性の嫁入り道具か社交場とした感があるが本来は武将がするもの。戦いの修羅場を離れて武器を捨て、ほのかに漂う香のかおりを聞いた瞬間、彼らははじめて生きている事の喜びを肌身で感ずる事ができたに違いない2015/09/15
ナウラガー_2012
0
名維持維新頃の薩摩人は「海軍」へ、長州人は「陸軍」へ進む傾向/正子は細川護立から中国の陶磁器の魅力(唐三彩)を教わった/陶器(土もの):金属分の多い土で低温で焼かれたもの、磁器(石もの):金属分が少なく珪酸を多く含んだ土を高温で焼いたもので完成品を叩くと金属音がする/よびつぎ:割れた茶碗を繋ぎ合せて復元させたもの→「筒井筒:秀吉の子供が割ってしまったものを細川幽斎が歌を詠んでこれを救った故事があり、利休が後に修理した。これを布地に求めたものが”辻が花(絞りで染めた上に椿や藤の花を墨で描いたりしたもの)”2015/09/15
きなこ丸
0
白洲次郎は男前だが正子も男前であるな。2019/06/04