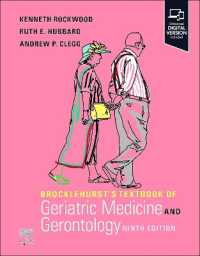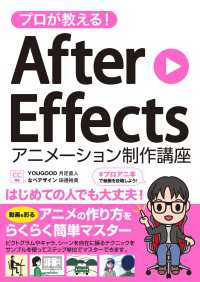出版社内容情報
タブーを犯さなければ生産者は生きていけない
安さだけの追究が、食品偽装を引き起こす
本物には、必要な「適正価格」がある。買い支えよう!日本の素晴らしい食を!!
安い食を求め続けるということは、身近な日本国内の生産者・製造業者を生活できない状況に追い込んでいくということでもあるのだ。本書で言いたいことはひとつだ。それは「日本の食品価格は安すぎる」ということである。最近、マーケティング業界の集まりなどでも、「農業などの第一次産業を復興させるためには、価格を少なくとも1.5倍、できれば2倍くらいに上げなければ無理でしょう」という話をする。聴衆が期待しているのは、「様々な工夫によって、良質なものを低価格で提供できるビジネスモデルが成り立つんですよ」といった話なのはわかっている。けれども、そんなムシのいい話は、そもそもどこにも存在しない。新鮮で、安全で、美味しい食品は、高くて当たり前のものなのだ。
●食品偽装は消費者にも責任アリ?
●モノを作る人の顔が見えていない
●「本物」に必要な適正価格とは
●1本200円以下の地鶏は疑うべき
●化学調味料入りの方が売れる!?
●こだわりの豆腐は1丁300円!
●市場から消えつつある伝統野菜
●「卵は物価の優等生」の裏側
●共感できる商品を「買い支える」
●安全のコストは誰が払うのか?
山本 謙治[ヤマモト ケンジ]
著・文・その他
内容説明
安さだけの追求が、食品偽装を引き起こす。タブーを犯さなければ生産者は生きていけない。食品偽装の根源に迫る。本物には、必要な「適正価格」がある。買い支えよう、日本の素晴らしい食を。
目次
第1章 安すぎる「食」が偽装を引き起こす(「意図的に引き起こされた」事件;「消費者にも問題がある」という発言 ほか)
第2章 「本物」に必要な適正価格(日本の漬物は安すぎる;日本の豆腐は安すぎる ほか)
第3章 「庶民の味方」はいつまで続く?(日本の牛肉は安すぎる;日本の豚肉は安すぎる ほか)
第4章 「地元率」という大切なファクター(日本のラーメンは安すぎる;日本のハンバーガーは安すぎる ほか)
第5章 消費者の行動が日本の「食」を支える(購買という「権力」を正しく行使する;「こういう商品はないの?」と声を上げよう ほか)
著者等紹介
山本謙治[ヤマモトケンジ]
1971年、愛媛県に生まれ、埼玉県で育つ。1992年、慶應義塾大学環境情報学部在学中に、畑サークル「八百藤」設立。キャンパス内外で野菜を栽培する。同大学院修士課程修了後、(株)野村総合研究所、青果流通の(株)シフラを経て、2005年、(株)グッドテーブルズ設立。農産物流通コンサルタントとして活躍中。本業の傍ら、ブログ「やまけんの出張食い倒れ日記」を書き続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
さきん
印度 洋一郎
まさる
いもムシ