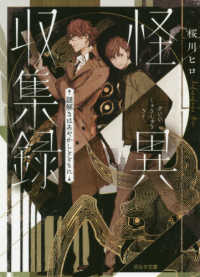出版社内容情報
日本の「鉄道構造物」のすべてを著者所有の貴重な写真と図面で紹介します。2003年にJTBから発刊された『鉄道構造物探見』は、日本の「鉄道構造物」であるトンネルや橋梁の構造を初めて具体的に説明した決定版的鉄道書として、現在も鉄ファンから絶大な支持を受けています。そして、著者はこの1冊で全国の鉄道ファンから鉄道構造物のカリスマとして崇められています。
トンネルや橋梁は、鉄路だけでなく、道路にも当然存在します。しかし、道路を走る自動車は大型トラックでも1台当たり20?25トンが最大重量ですが、機関車の重量は、1両100トン前後にも達します。このため鉄路では道路よりも頑丈なトンネルや橋梁を設計しなければなりません。また、自動車のように急勾配や急カーブがきかないため、路線の選定に制約条件が多くなり、山岳地では長いトンネルを掘って峠をくぐり抜けなくてはならず、明治時代から鉄路は、大規模な「鉄道構造物」を率先して造り続けてきました。
本企画は「鉄道構造物」の造られた歴史的背景や経緯、設計思想などをより細かく盛り込んだ構成になっています。
著者は、全国の「鉄道構造物」のどこに工夫の跡があるのかを現地取材で実際に照合し、確認しています。なぜこのようなトンネルを造ったのか、なぜこのような形の橋が架かっているのかを明解に解説します。『鉄道構造物探見』発刊から10年。より詳細に、より具体的に日本の「鉄道構造物」のすべてを著者所有の貴重な写真と図面で紹介します。
2012年に中央高速道の笹子トンネルで老朽化による悲惨な事故がありました。鉄路での事故ではありませんが、鉄道生誕140年を越え、老朽化も含め、鉄路トンネルの安全性も危惧され、注目されています。
本書は鉄ファンだけでなく土木構造物の鑑賞辞典としての性格も持ち合わせています。土木事業者にも充分に訴求できる著者の知名度と内容です。
【目次】
巻頭カラー口絵/写真でたどる鉄道構造物の歴史
第1章 鉄道構造物の種類と特徴
第2章 橋梁
第3章 高架橋
第4章 トンネル
小野田 滋[オノダ シゲル]
著・文・その他
内容説明
日本の鉄道輸送を黙々と支え続けてきた鉄道構造物。今、その全貌が明らかになる。撮影地として有名な橋梁から廃線跡にひっそり残るトンネルまで、鉄道構造物を知ると鉄道の新しい世界が広がる。
目次
巻頭カラー 写真でたどる鉄道構造物の歴史(鉄道橋梁の始まり;鉄道トンネルの始まり ほか)
第1章 鉄道構造物の種類と特徴(鉄道構造物の諸相)
第2章 橋梁(鉄道橋梁とは何か;橋梁の分類 ほか)
第3章 高架橋(高架橋の特徴;高架橋の種類)
第4章 トンネル(トンネルの分類;トンネルの断面 ほか)
著者等紹介
小野田滋[オノダシゲル]
1957年愛知県豊橋市で生まれ、西宮市、東京都、広島市、名古屋市、浜松市で育つ。1979年日本大学文理学部応用地学科を卒業し、日本国有鉄道入社。東京第二工事局、鉄道技術研究所地質研究室、西日本旅客鉄道大阪構造物検査センター、海外鉄道技術協力協会などを経て、現在、鉄道総合技術研究所勤務。土木史、鉄道史について研究し、文化庁や国立科学博物館などの依頼に協力して近代化遺産の調査にも従事している。土木学会フェロー。博士(工学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
ぎんりん
やまほら
-
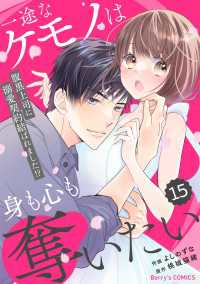
- 電子書籍
- comic Berry's 一途なケモ…
-
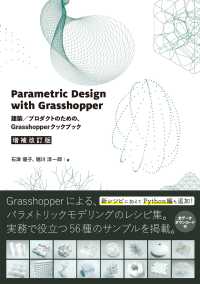
- 電子書籍
- Parametric Design w…